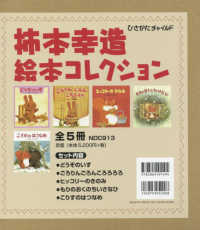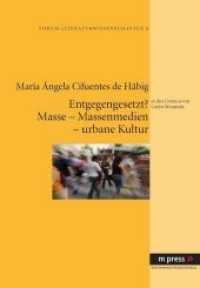出版社内容情報
日本人は、生の力を肯定する思想とともに、生の暗さを凝視する思想を愛した。この地獄の思想こそ、人間の苦悩への深い洞察と、生命への真摯な態度を教え、日本人の魂の深みを形成してきた。源信、親鸞、紫式部、世阿弥、近松門左衛門、宮沢賢治、太宰治などは、みな現世に地獄を見た人びとであった。これら先人の深い魂の苦闘の跡を知らなければならない。生命の強さは、どれだけ暗い生の事実を見つめるかによって示されるからである。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ジョンノレン
54
ことある毎に引っ張り出して読んでいる、宗教のみならず古典芸能を含む文学にもしっかり踏み込んだ梅原版日本の地獄観の集大成。今回は能の謡曲集を読んでいたら地獄の思想の世阿弥の章で「蝉丸」と「綾鼓」を取り上げていたのを思い出して改めて読んでいたら源氏物語や平家物語も謡曲に絡んで来たのでそちらもと並行読みしているうち結局ほぼ全般に目を通す結果に。かつて読んだ時からたっぷり時間と経験を積んだせいか、少しは梅原氏の視座に近づいて来たような、他方で同氏ちょっと膨らましすぎではと思う箇所も。定点観測もまた楽しからずや。2025/09/23
こうすけ
29
スーパー能制作のドキュメンタリー番組を見て、その人柄にハマった梅原猛さん。日本文学は地獄の思想の影響を受けているという説のもとに、源氏物語や平家物語、近松、宮沢賢治、太宰治などの作品をたどってゆく。源氏物語を「もののあはれ」としてではなく、仏教文学として捉えてゆく面白さ。積読中だが読んでみたくなった。そして、あくまで個人の地獄を描く日本文学の系譜のなかで、地獄という世界そのものを描いてみせた平家物語。著者の、地獄を見つめることで生を肯定しようとする姿勢と、執筆時のベトナム戦争に対する批判的な視点が良い。2021/02/28
樋口佳之
27
読んだのは電子本ですが、その底本は2009年5月15日 第58版 版を重ねた事に納得の内容でした。/紫式部は人間のどうにもならない姿を凝視する人間であった。そういう煩悩にみちた人間こそ、仏が救う。仏が救わなかったら私が救おう。『源氏物語』を書く式部自身が救う人でもあり、救われる人でもあった/宣長のように、あわれ、あわれといっているだけでは、とてもこの物語の深さはわかりはしない2019/01/19
三柴ゆよし
12
凄い本を読んだ。地獄の思想によって貫かれた宗教史であり、哲学史であり、文学史である。同時に、著者自身の心奥に沸々として煮えたぎる地獄の景色が、その行間からさながら透かし絵のごとく浮かび立ってくる、物凄まじさ。生きることの楽しくて楽しくてしかたない人たちがいる。けれどそうした人たちにおいては、生の片面しか見えていないと著者は言う。自己の内部にある地獄にしかと眼を据えたとき、はじめて生の本質が見えてくる。これまで一体になにを求めて文学作品を読んできたのか、本書を読んではじめてそれがわかったように思う。2010/06/05
スターライト
11
地獄の思想の系譜を仏教を中心に見ていく第一部、その思想が文学にどのように影響を与えたかを考察する第二部で構成。地獄について考えることは、人生について考えることとほぼ同義であることではないかと本書を読んで感じた。極楽は地獄と対になって存在し、現世が地獄であるからこそ人は死後は極楽に生まれ変わることを望む。現世が極楽であるならば、地獄という発想は出てこない。欲望にまみれた自分、社会を見つめた文学者(能・戯曲の芸能を含む)たちの歩みを地獄の思想の観点から解き明かす刺激的な書物であった。2020/02/09