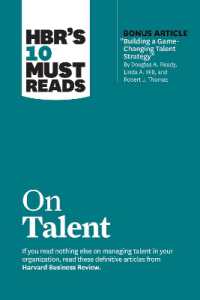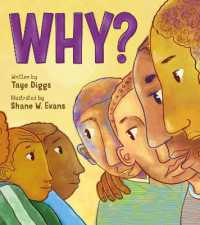出版社内容情報
『田中角栄研究』『宇宙からの帰還』『脳死』など、ジャーナリストとして膨大な著作を残した「知の巨人」は、なぜ晩年、あえて非科学的な領域に踏み込み、批判を浴びたのか……。
「語り得ない領域」に触れる詩や信仰の言葉を弄ぶことを禁じて、ファクトを積み重ねて突き進んでいた立花が、最晩年に小説や詩が醸す豊潤な世界に身を委ね、宗教と和解する必然を描きだした渾身のルポルタージュ。現代社会に問いを立て続け、書き、疾走した立花隆の原点と到達点を解き明かす。大江健三郎氏との未公開対談「創作と現実の間」を収録。
内容説明
神の言葉に背を向け、ジャーナリズムの限界を問い続けた。『田中角栄研究』『宇宙からの帰還』『脳死』など、ジャーナリストとして膨大な著作を残した「知の巨人」は、なぜ晩年、あえて非科学的な領域に踏み込み、批判を浴びたのか…。「語り得ない領域」に触れる詩や信仰の言葉を弄ぶことを禁じて、ファクトを積み重ねて突き進んでいた立花が、最晩年に小説や詩が醸す豊潤な世界に身を委ね、宗教と和解する必然を描きだした渾身のルポルタージュ。現代社会に問いを立て続け、書き、疾走した立花隆の原点と到達点を解き明かす。未公開対談「創作と現実の間」(大江健三郎×立花隆)を収録。
目次
1 北京の聖家族
2 焼け跡の知的欠食児
3 二十歳のころの反核運動
4 現代詩と神秘哲学
5 ヤクザと言語哲学―週刊誌記者時代
6 『論理哲学論考』の磁力圏―「田中角栄研究」
7 ジャーナリズム+αへ―『宇宙からの帰還』
8 もうひとつの調査報道―『脳死』
9 相転移と踏み止まり―『脳死体験』
10 東大教授になったジャーナリスト
11 「立花先生、かなりヘンですよ」
12 ニュー・サイエンスと「知の巨人」
13 「あの世で会おう」―『武満徹・音楽創造への旅』
14 回帰と和解のとき
創作と現実の間―(対談)大江健三郎×立花隆
著者等紹介
武田徹[タケダトオル]
1958年生まれ。ジャーナリスト、評論家、専修大学文学部教授。国際基督教大学大学院比較文化研究科博士前期課程修了。著書に『流行人類学クロニクル』(サントリー学芸賞受賞)など(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
パトラッシュ
trazom
ころこ
ぐうぐう
せらーらー