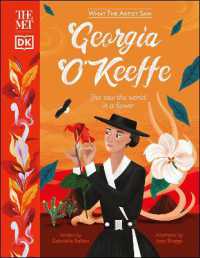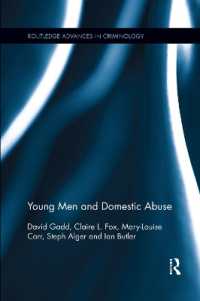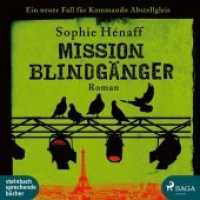- ホーム
- > 和書
- > 人文
- > 文化・民俗
- > 文化・民俗事情(日本)
出版社内容情報
江戸時代。50歳で隠居したのち、江戸中を訪ね歩いた大名がいた。五代将軍綱吉のお側用人・柳沢吉保の孫、信鴻(のぶとき)だ。彼が物見遊山で訪れた範囲は、日本橋・浅草周辺はもちろんのこと、王子、向島、目黒方面と、日に何十キロと徒歩で歩いては、身分によらずそこに暮らす人々と交流し、ありのままの江戸を日記に書き残していた。活気に満ちた江戸の描写溢れる信鴻の『宴遊日記』を元に、その軌跡を追う!
内容説明
50歳を前に「ご隠居」となり、江戸中を訪ね歩いた大名がいた―活気に満ちた町の暮らしが、貴重な資料と豊富な図版で甦る!大和国郡山藩第二代藩主・柳沢信鴻。彼は四十九歳で隠居すると、江戸市中を歩き回り、その情景を書き記した。日本橋・浅草周辺はもちろんのこと、王子、向島、目黒方面と、一日に何十キロと歩いては、そこに暮らす人々との交流を楽しんだ。活気に満ちた江戸の描写溢れる信鴻の『宴遊日記』を元に、その足取りを追う!
目次
第1章 江戸の物見遊山
第2章 ワンダーランド浅草
第3章 側室と訪ねる吉原
第4章 風流な江戸の空模様
第5章 見世物と開帳の両国・亀戸
第6章 聖と俗の上野
第7章 富籤の湯島と天下祭の神田
第8章 盛り場の芝居町
第9章 秋は護国寺から雑司ヶ谷へ
第10章 飛鳥山からの閑歩
第11章 風光明媚な増上寺・祐天寺
第12章 恵まれた江戸庶民
著者等紹介
青木宏一郎[アオキコウイチロウ]
1945年、新潟県生まれ。千葉大学園芸学部造園学科卒業。株式会社森林都市研究室を設立し、ランドスケープガーデナーとして、青森県弘前市弘前公園計画設計、島根県津和野町森鴎外記念館修景設計などの業務を行う。その間、東京大学農学部林学科、三重大学工学部建築科、千葉大学園芸学部緑地・環境学科の非常勤講師を務める。現在、和のガーデニング学会会長(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
パトラッシュ
onasu
ようはん
tama
カズザク