内容説明
戦争は人類共通の自然状態に根ざした現象なのか?それとも文化が発明したものなのか?戦争・戦略の分野で注目されている新進気鋭の研究者が、生物学、人類学、考古学、歴史学、社会学、政治学の最新成果を脱領域的に横断し、多角的に徹底検証する。
目次
第1部 過去二〇〇万年間の戦争―環境、遺伝子、文化(はじめに―「人間の自然状態」;平和的それとも好戦的―狩猟採集民は戦ったのか?;人間はなぜ戦うのか?―進化論の視点から;動機―食糧と性;動機―入り組んだ欲望;「未開の戦争」―どのように戦われたか?;結論―人類の発展状態における戦闘)
第2部 農業、文明、戦争(はじめに―進化する文化的複雑性;農耕社会と牧畜社会における部族戦争;国家の出現における軍隊)
著者等紹介
ガット,アザー[ガット,アザー][Gat,Azar]
テルアビブ大学政治学部エゼル・ワイツマン(Ezer Weitzman)国家安全保障講座担当教授。1959年生まれ。イスラエル・ハイファ大学卒。テルアビブ大学(修士)、英オックスフォード大学(博士)、ドイツのフライブルク大学、米エール大学、オハイオ州立大学、ジョージタウン大学で研究や教育に携わってきた経歴を持つ。軍事史および戦争・戦略研究の分野で数多くの著作を発表(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
absinthe
170
ホッブス的世界観を支持している。戦争が始まったのは農耕開始以後ではなく、狩猟採集民も同様に戦争を行っていた。様々な都市国家で排水溝やら灌漑用とかさまざまに解釈されていた謎の遺構は、ほとんどが城壁であり攻撃への備えだった。狩猟採集から農耕、都市国家、帝国への進化の様子は異なる文化間で驚くほどの類似を示し、進歩のほとんどが戦争と関連していた。支配体制は様々あったが、その目的は戦闘集団の維持のやり方に深くかかわっていた。2016/01/14
アナクマ
20
「戦争は最近になって現れた文化上の発明ではない」「危険で死を招く活動の背後にはどのような理由が存在するのだろうか」上巻半分までが第一部で、 ”未開“(農耕以前)の戦争について。以下目次から。◉なぜ戦うのか。動機(食糧、縄張り、水、住まい、原材料、性、支配、復讐、遊び、冒険、加虐嗜好、恍惚)。どのように戦われたか。このあたりがとくに興味をそそる。が、これは時間をかけてじっくり取り組まねば消化しきれないコッテリさ。2022/12/26
たぬきオヤジ
17
ルソーかホッブスか。高貴な野蛮人は正しいか。本書は人間は平和を愛するはずだという思い込みに警鐘を鳴らす。(戦争は不可避だとは言っていない。)人間が戦争に至る過程を紀元前から現代にいたるまでの歴史から、量的な絵ヴデンスを交えて説明する。2019/11/22
エジー@中小企業診断士
11
執筆は1996年から2005年。米国同時多発テロが発生した時期だが本書の動機や議論には全く無関係と序文にある。なぜ人類は戦争をするのか。男性ホルモン、テストステロンにより明らかに男性は女性より攻撃的。人間の本性なのか、文化や農耕による富の蓄積が原因か。この議論はホッブズ対ルソーの対立的な主張が有名だが、考古学的な証拠によれば狩猟採集民の暴力による死亡率の高さはホッブズ的な捉え方が現実に近いと示す。食糧と性、復讐などの動機。人間の自然状態も他の動物と同様に結局は極度に不安定で暴力による死に満ちたものだった。2023/09/16
smatsu
7
真摯な姿勢で書かれた優れた研究書ですが非常に内容が濃く、記述に無駄も無いため飛ばし読みもできない。一通り読むだけでかなり大変です。戦争の歴史はほぼ人類史と同義だと思うので凄い仕事だと思う。1人の人間がよくこれだけの情報をまとめあげられるものだと感嘆します。上巻の内容は人類学と生物学、考古学的な視点から論ずる第1部と古代の部族社会から国家の発展の歴史を論ずる第2部の途中まで。一回読んだだけでは消化しきれないのでまたいつか時間を取ってもう一度ノートを取りながら読んでみたいと思います。2019/04/07
-
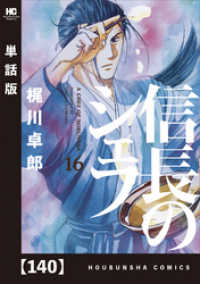
- 電子書籍
- 信長のシェフ【単話版】 140 芳文社…








