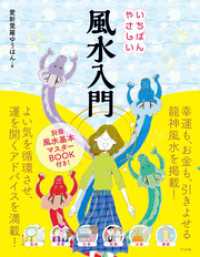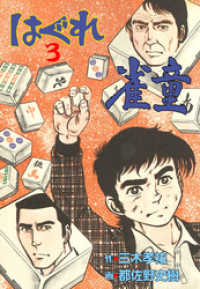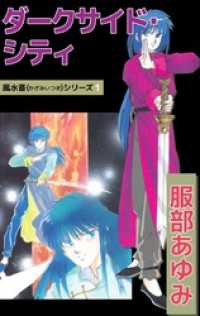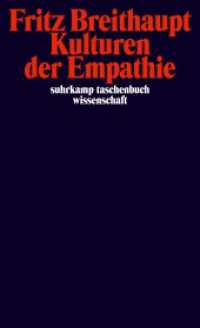内容説明
名人・五代目小さんが得意中の得意だった54席。師匠のもとで長く内弟子として過ごした著者が、身近で聞いた噺の精髄、話術の要諦を公開し、後世に伝える。柳家小三治によるエッセイ「我が師五代目小さんの落語」収録。
目次
青菜
言訳座頭
意地比べ
芋俵
浮世根問
うどん屋
馬の田楽
おせつ徳三郎
親子酒
笠碁〔ほか〕
著者等紹介
柳家小里ん[ヤナギヤコリン]
本名、安田雅行。落語家。社団法人落語協会所属。1948年、東京都台東区に生まれる。1969年1月、五代目柳家小さんに入門。前座名「小多け」。1974年5月、二ツ目に昇進して改名、「柳家小里ん」。1983年9月、真打昇進。国立演芸場花形新人演芸会新人賞銀賞、同花形若手演芸会新人賞金賞、同花形新人大賞などを受賞
石井徹也[イシイテツヤ]
放送作家。1956年、東京都港区に生まれる。早稲田大学落語研究会在籍中から『落語界』『落語』などに落語家評を執筆(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
姉勤
33
この頃、「五代目小さん」ばかり聴いている。本書を読んでその理由がわかった気が。54の演目を、内弟子だった小里ん師匠へ石井徹也氏が聞き手となり、亡き小さん師の落語と、聞き継いだ先代・先々代小さんの芸風、先人や同時代の噺家の工夫と自身の手入れ、それを含め、格別の”藝”を語っていく。自然に演っているようで計算尽くした間や目線、人物に成りきり、彼らならこうするであろう行動や口調を究理する。しかし、そんなことを客に感じさせない、人(にん)の凄み。これは何度も読みたい。言わずもがなだけど、人間国宝は伊達じゃない。2019/02/19
6だ
3
小さんの弟子(小里ん)が教わったり見聞きしたその姿や芸風を聞き手(落語好きの放送作家)と語り合う。落語にこれが正解というものはないだろうが、「小さん落語」における理想という意味での正解、柳家伝統の「了見」、というものがどういうものだったかは見えてくる。以下抜書き「なんでこの科白が要るんだろうって考えなきゃいけない」「一つの噺に対して疑問がなくなったらオシマイだ」「ギャグを言うために落語を演ってるんじゃない」「得意なところは長く演るな」「登場人物がちゃんと演じられている、という作り方ならば落語は面白くなる」2012/07/01
qoop
2
内弟子だった小里ん師が聴き、解釈した五代目小さんの芸談。落語の、芸の広さ深さがいっぱいに語られた一冊。小さんと云うと〈狸を演るには狸の了見になれ〉ばかり繰り返されるが、その一言の奥には驚くほど豊穣な世界が広がっていた。ここに達するまでどれほどの修練が必要か、この引力圏を脱するためにどれほどのパワーが必要か。演者だけでなく、聴く側にも覚悟が求められそうな内容で、正直クラクラした。2012/06/13
Kuliyama
1
落語を語るのにこれほど考えていることを初めて知りました。また小さん師匠の話を聞きたくなりました。2016/02/10
佐藤幾優/Ikuma Satou
1
小里ん師談 今まで讀んだ乏しい落語系の經驗のなかではダントツに濃い一冊 「口傳」の書 たとへば四代目の教へや言及に關して五代目の自傳よりも斷然濃い これは小里ん師他が五代目から「四代目はかうだった」と教はったのが載ってるから この構造は凄くよくわかる2014/03/10