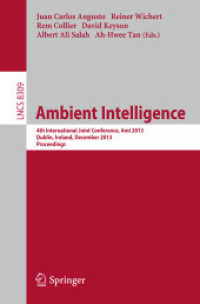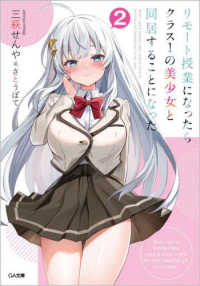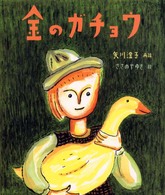出版社内容情報
唐から帰国後の空海は、八面六臂の活躍を続ける。その死の秘密をも含めて描く完結篇。芸術院恩賜賞に輝く司馬文学の最高傑作の新装版。
著者等紹介
司馬遼太郎[シバリョウタロウ]
1923(大正12)年、大阪に生まれる。大阪外国語大学蒙古語科を卒業。1959(昭和34)年、『梟の城』により第四十二回直木賞を受賞。67年、『殉死』により第九回毎日芸術賞、76年、『空海の風景』など一連の歴史小説により第三十二回芸術院恩賜賞、82年、『ひとびとの跫音』により第三十三回読売文学賞(小説賞)、83年、「歴史小説の革新」により朝日賞、84年、『街道をゆく―南蛮のみち1』により第十六回日本文学大賞(学芸部門)、87年、『ロシアについて』により第三十八回読売文学賞(随筆・紀行賞)、88年、『韃靼疾風録』により第十五回大仏次郎賞をそれぞれ受賞。1991(平成3)年、文化功労者に顕彰される。93年、文化勲章受章。日本芸術院会員。1996(平成8)年2月、死去
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
Gotoran
58
下巻では遣唐使として長安を訪れ、青竜寺で恵果に会い、密教を伝授されて、帰朝後真言密教を立ち上げ、死去するまでの足跡が綴られる。その中で主に当時の政情と共に最澄との関係(交流と確執)が記述されている。空海に膝を屈して師事を仰ぐ最澄は、経典のみの学びだけで密教を体得しようとするが、やがて空海は行法と信仰重視する密教では片手間な学びの姿勢では無理があると戒めることとなり、空海と最澄の確執が生じたと云う。空海を見事に描き切った司馬遼の史実に沿った姿勢と素晴らしい文章力に魅了された。再び高野山を訪れたいものだ。2017/05/11
ロマンチッカーnao
18
随筆のような散文のような味わい深い小説を読み終わりました。確かに空海の居た風景を感じれましたね。空海そのものとか、空海の真言宗の内容とかそういうものにはあまり触れませんが、空海が存在した時代の空気を感じれました。空海、嵯峨天皇、橘逸勢の関係性、最澄の生真面目な人間性と空海の対応のえげつなさとか、しかしどこを切り取っても、空海は、天才とか英雄とかそういうのをもう一つ超えた存在だったんでしょうね。司馬さんには『空海と最澄のいた風景』としてもう一作書いてほしかったな。2021/02/01
ろし
15
空海が恵果に会ってからはの、進展がめざましく綴られている。そもそも、唐に渡る前に相当の修行をしており、修行というても滝に打たれたり(打たれたかもしれないけど)と、いうより密教の体系化ほぼ完成したようで、さらに恵果に会った時は、サンスクリット語や言語哲学も充分であったよう。最澄との対比も興味深く、全くもって対照的なふたりを伺うことが出来た。なんか、凄いお大師さんであるが、考え事をする際にはじっと座ってというよりも、山野を駆け巡りながらだったのではないか、というところにおそれ多くも親近感がわくのです。2017/11/13
nemunomori
11
空海の帰国から高野山で迎える晩年まで。平城帝と嵯峨帝の諍いが薬子の乱へと発展する不穏な時代、空海の密教が完成する。藤原一門の確執、奈良仏教と密教、最澄と空海。同じ時代を生きた人々の息遣いをありありと感じた。空海のただならぬ意志の強さは、人を惹きつけてやまない魅力であるとともに怖ろしくもある。個性が突き抜け過ぎていて感情移入など考えられない。なるほど、だから「風景」なんだと思った。あとがきも本分同様に読み応えがあり面白い。2015/08/10
湯一郎(ゆいちろ)
9
昭和50年という僕の生まれた年に書き終わった小説。あとがきにあったが、仏教的な用語を極力使わずに書かれていた。言われてみれば!だ。だからこんなにわかりやすかったのかと驚く。密教とは何かを描くのであればまた別であろうけど、空海がどういう存在だったのかはわかる。もちろん稀代の大天才の概略でしかないけど。最澄とのやりとりはすれ違いのようで切ない。そして天台宗との確執は2009年まで続く。『阿吽』の今後がますます楽しみになった。2018/05/25
-

- 和書
- 映画の隔たり