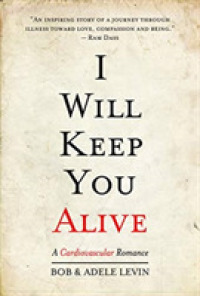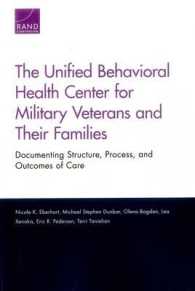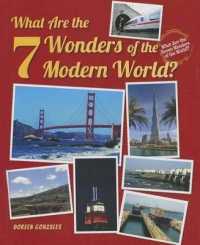内容説明
一人の無能な将軍が恣につくりあげた文化が、その後の日本人すべての美意識を決定づけた。著者が半世紀にわたって深く関心をもちつづけてきた東山文化。それはどのようにして生まれたのかを、愛着をこめて描く。
目次
序章 東山時代と燻し銀の文化
第1章 父義教の暗殺
第2章 乳母と生母の狭間で
第3章 将軍を取り巻く男と女
第4章 応仁の乱と東山趣味
第5章 東山山荘の造営
第6章 雪舟・一休と日本文化の心
第7章 歌人義政と連歌芸術
第8章 花道と築庭と
第9章 茶の湯の誕生
第10章 晩年の義政
著者等紹介
キーン,ドナルド[キーン,ドナルド][Keene,Donald]
1922年ニューヨーク生まれ。コロンビア大学、同大学院、ケンブリッジ大学を経て、53年に京都大学大学院に留学。現在、コロンビア大学名誉教授、アメリカ・アカデミー会員、日本学士院客員。文化功労者。勲二等旭日重光章受章。菊池寛賞、読売文学賞、毎日出版文化賞など受賞多数
角地幸男[カクチユキオ]
1948年東京生まれ。早稲田大学文学部卒業。ジャパンタイムズ編集局勤務を経て、現在、城西大学女子短期大学部助教授
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
あっきー
14
✴3 NHKが銀閣寺を特集していて義政がこだわって建てた建物が4畳半の障子の部屋だったのを紹介していた、先日方丈記を読んで自分の部屋も方丈だと思ったのだが同時代の将軍様もそんな狭い部屋で風月を楽しむ生活を理想としたらしい、それは隠遁生活をするためではなく、好みが同じで心静かに絵画その他を味わうことのできる人を招いて和歌を詠むなど仲間とのつきあいを楽しむ場所だった、 応仁の乱や当時の文化も分かりやすく、文章も装丁も落ちついた渋い雰囲気の良い本だ2020/03/12
犬養三千代
6
2003年1月発行。 一つ一つの章立てが短く読みやすかった。そして、内容が濃い。 今の日本人に沢山の文化遺産を残した。「美意識」過剰な「人」としての義政を禅、絵画、連歌、華道、茶の湯、源氏講釈、築庭、書道など様々な分野を分析しておられる。 ときに外国人としての視点もある。 百年後に残したい良書。 政治家、武人としては最悪。 禅僧たちは素晴らしい文化、芸術の担い手たった。2018/05/31
ホンドテン
0
図書館で。雑誌連載の評論をまとめた、文章まで平易な評伝(翻訳であるからでもある)。辻との対談(2014)につながる部分は多い。後段の東山山荘に集約される文化的功績の部分は連歌、作庭、茶道、華道の成立のさわりとなっており、いずれも新知見で勉強になった。思えば英語圏の初学者への紹介、解説の性格もあるので、そのレベルと同列では恥じ入るべきかもしれない。ついでながら読後、慈照寺(銀閣)と西芳寺を訪れたくなる。2017/01/21
しんさん
0
テステス2015/05/13
かばんもち
0
文化・芸術面では現代においても義政の影響はありありと感じる。「銀閣寺を建てた人」以上の認識をもたれて良いはずなんだが・・・。もっと評価されて良い人物だと思う。2013/02/14