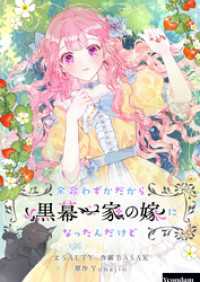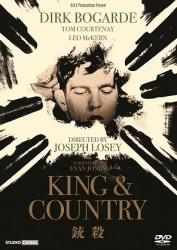内容説明
戦後日本を席捲した大塚史学への挑戦、今西錦司・梅棹忠夫らとの出会い、ウォーラーステインに先駆けた世界資本主義論、茶、時計、米などの「モノ」を糸口にグローバル・ヒストリーを編み出した経済史家がその半生、方法、学問の醍醐味を軽妙に語る。
目次
1 戦後日本の歩みとともに(大塚史学への挑戦;経済史から生活史へ)
2 フィールドワークが開拓した生活史(イギリス・ヨーロッパをフィールドワークする;アジアをフィールドワークする;「領事報告」をフィールドワークする)
著者等紹介
角山栄[ツノヤマサカエ]
堺市博物館館長、和歌山大学名誉教授、奈良産業大学名誉教授。経済史専攻。1921(大正10)年大阪市生まれ。45年京都大学経済学部卒。50年より和歌山大学に勤務し、61年経済学部教授、67年学部長、75年学長を歴任。87年より奈良産業大学教授。93年から堺市博物館館長
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。