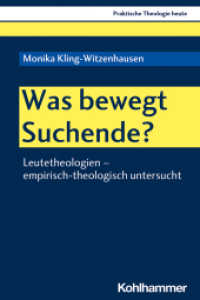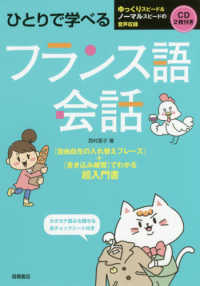出版社内容情報
一発の銃弾からすべては始まった――。戦争は泥沼化し、毒ガス・戦車・機関銃など大量殺戮の武器が初めて世に現れた。屈指の軍事ジャーナリストが描いた、世界初の「近代戦」とは。
内容説明
パンドラの筺を開けたのは、一発の銃弾だった。毒ガス、機関銃、重砲、戦車、爆撃、泥沼の塹壕戦…「近代戦」というシステムが殺戮の世紀の扉を開く。
目次
第1章 戦争の原因
第2章 両陣営の兵力
第3章 両陣営の作戦計画
第4章 クリンチ―1914年
第5章 行詰り―1915年
第6章 “相討ち”―1916年
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
skunk_c
77
著者はイギリスを代表する戦史家であり、戦闘の展開については極めて詳細に描かれている。ただしフランス、特にジョッフルやフォッシュに厳しく、全体として「イギリスびいき」な印象は否めない。本書の価値を高めているのが東部戦線、とりわけルーマニアの参戦と崩壊についてで、これについて詳細に書かれたものは初めて読んだ。コンパクトなまとめがコラムのような形で挿入され、地図も豊富かつ適切で情勢がよく分かる。ただし年代別記述でありながらアジア(日本)は完全に捨象されている。やはり本質は欧州大戦ということか。2024/03/06
富士さん
5
初めて読んだときはひたすら退屈でしたが、読み直してみるとその密度に圧倒されました。本書のテーマは、開戦以外の選択肢がありえないように合理化を極めた専門性や状況を計画に合わせるために有利さをわざわざ捨てるというお役所仕事が、それらと最も真逆にあるはずの戦争において現れた開戦の事情に最も代表的に表れています。ベルトコンベヤーで人間を戦場へ送り、ミンチに加工するだけが戦争ならおよそ何の芸もない。そんな単細胞生物化というヒトの進化に疑問を呈するのが第一次大戦という舞台を借りた著者のテーマであるような気がします。2018/02/26
ポルターガイスト
4
10年前の教員一年目のときに買って積んでいたが無理やり読んだ。少しは賢明になっている今なら絶対買わないだろう。軍事史の色彩が強く,銃後の社会などの記述は基本的になし,司令官の判断と作戦に焦点が置かれている。密度はすごいが,率直に言っておれにとっては退屈で,戦いの流れそのものだけなら途中に挟まれる要約コラムだけ見れば事足りると感じた。もちろんこの分野が好きな人には魅力的なのでしょうが。内容で言えば行き当たりばったりに始まった戦争だけあって戦争の展開もかなりズルズルしてるなという印象でした。2021/08/21
hijmsxxxx
1
リデル・ハートによる第一次大戦の歴史。欧州の地名に馴染みがないのと時間軸が行ったり来たりで、途中に挟まれるコラムを読むことによってなんとか追っかけられた。師団単位のお話が主体なんだけど、司令官が無謀な突撃を敢行して簡単に全滅してしまうことしばしばで、第一次大戦の時の人の命の軽さを実感した。2012/12/06
あれっさんどろ
0
時系列がわかりづらかったなぁ