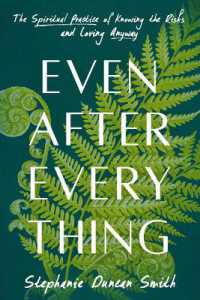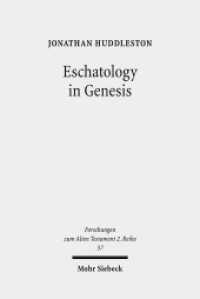出版社内容情報
精神科医の六麦は、少年院で知能に問題がある少年少女を見てきた。彼らにはある一定の傾向があり、問題を抱えながら更生を進めている。恋人から教わり覚醒剤に嵌まり込んだ大西瑠花だったが、少年院での暮らしで更生できるか、その姿を描く――。そして、窃盗を繰り返し少年院へ入った三鉢友典のケースも収録! ――更に話題を集める第9巻!
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
しいたけ
55
知的な発達に顕著な遅れがあるのに中学校では「やる気がない・サボり」と扱われる。少年院での工夫されたトレーニングに感銘を受けるが、少年院にまで行かなければ適切な対応をして貰えなかったと考えるとつらい。私のホームの子の件で中学は特別支援学級に入れて欲しいと活動したことがあった。小学校の担任も中学で普通級の授業を受けるのは無理と進言してくれたが結果は普通級。理由は「1時間座っていられるから」。何にもわからないまま1時間座っていることの辛さをわかって貰えなかった。結局中学で不登校に。特支の定員もあるがやはり無念。2025/02/11
Mr.deep
5
認知機能強化トレーニングの内容が高度過ぎて戦慄した。正直付いてける気がしない2024/08/09
かなっち
3
子供を取り巻く環境はとっても危険なことや、子供を守るのは親の愛情が大切なことを、毎回実感させられるシリーズの第9巻です。前巻に続いての、家に居場所がない女の子が彼氏に愛情を求め、その男の影響で覚醒剤に嵌り、どんどん泥沼に落ちていったケースが前半に描かれていました。後半は窃盗を繰り返し少年院へ入った男子生徒のケースで、どちらも問題のあった家庭だったので胸が痛んだのです。学校の先生の奮闘ぶりと少年の懐き具合に救われる思いですが、同じことを望むのは、現在の疲弊している先生たちには難しいだろうと感じました。2024/09/17
直人
2
たたき台が実話ということなので,はっきりした結論が出ないのも,この物語の特徴。 薬物の禁断症状が解けてめでたしめでたしではなく,少年院からの退院後に,また染まるのではないか?という不安も描かれている。 現実でもそう。 依存というのはそういうもの。 覚せい剤というのは脳がその快感を覚えてしまっているので,離脱するのが難しいと聞いたことがある。 今巻の後半で描かれるのは,知的障害を抱える子どもたちが,社会により適応しやすくなるための教育風景が描かれる。 先生方には頭が下がる。2024/10/23
笠
2
3.5 新刊読了。窃盗少年と特別支援コーディネーターのエピソードは日本中で同じようなことが起きてそう。中学でも特別支援学級はあるはずだが、小6時点でかなり成績も向上していただけに、通常学級を選んだことが裏目に出てしまったのかもしれない。あの絵を見れば数式の前に教えることがあるはず…とはいうが、教員は指導要領とカリキュラムにしたがって担当教科を教えることだけで一杯一杯なんだよな。実際問題、特別支援学級以外での配慮には限界があると思う。2024/08/24
-

- 電子書籍
- 天声人語 2019年1月-6月