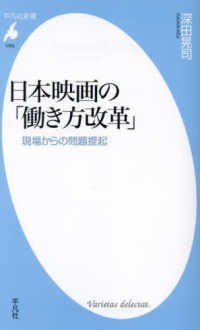感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ヴェネツィア
252
6篇の説経浄瑠璃を収録する。篇中で最も名高いのは「さんせう太夫」だろう。もっとも、それも説経としてではなく、あくまでも森鷗外の「山椒太夫」として知られているのだが。これらの各篇は、いずれも中世的世界観を濃厚に保持する作品群である。「さんせう太夫」も、もちろんそうである。この説経は、もともとは複数の語り物が融合して成立したかにも見える。タイトルがそもそも物語の全体を象徴するのではなく、敵役の名であることもそれを証左するかも知れない。また、この物語は「親子地蔵菩薩」の本地を語る、いわゆる「本地もの」である。⇒2025/09/14
ヴェネツィア
243
『しんとく丸』のみの感想。これまた中世ムードに溢れる説教浄瑠璃である。主人公のしんとく丸もまた申し子であった。この度、願をかけられたのは清水観音。また、この物語では、これ以降も度々清水観音の霊験が描かれる点が特徴的であり、観音は最後までしんとく丸に寄り添っていた。道行もまた3度も現れるが、これらのことからすれば、あるいはこの作品は説教の中でも古態を示すものであろうか。しんとく丸は、あわれにも継母の呪いによって「違例」となり、放浪を余儀なくされる。物語の大半は、この流離の過程を描くのだが、⇒2025/09/22
ヴェネツィア
216
説経浄瑠璃の中では最も波乱に富み、また中世的な要素も満載なのが『をぐり』である。まずは、本地もの。そして主人公のをぐりは蔵馬の毘沙門天の申し子である。異類婚姻譚もあり、貴種流離譚でもあり、手紙の謎解き、照手姫との婚姻、鬼鹿毛を乗りこなす英雄譚、死と復活、土車による村送り、道行…等々、もう全ての要素が揃っている。波乱万丈の物語。面白さでも群を抜く。表現こそ常套句の連続だが、それがまた何とも古雅な味わいを醸し出している。この物語も、あるいは元々はをぐりと照手姫との別々の物語が融合したのかも知れない。仮に⇒2025/09/18
ひさしぶり
20
「さんせう太夫」と「かるかや」 森鴎外の山椒大夫のもと 説経節 遊行神人や念仏僧の流れで庶民芸能の床本、底本に繋がっていくものと考えられるのでは。鴎外作品との違いは安寿姫の入水自殺はなく虐待死、大夫の繁栄はなく竹ノコギリを子にひかせ仇討ちをはたす。「一ひきひいては千僧供養、二ひきひいては万僧供養。」強烈です。又安寿姫はずっーと「姉御」で母上の身の上の場面に安寿の姫。「かるかや」は親子地蔵菩薩、「さんせう太夫」は金焼地蔵菩薩の縁起として語られる。2023/11/17