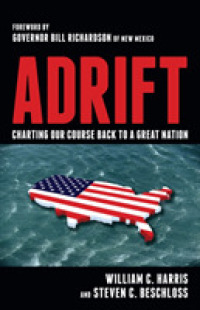出版社内容情報
総理大臣には働いてもらわなければならない。それも最初から、全力で。しかし、巨大タンカーのごとき日本政府を操るにはコツが必要だ。政治家の意思で、霞が関は動かせるのか。そして「本物の有事」に直面した時、政治は自衛隊などの実力部隊をコントロールできるのか。歴代最長の安倍政権で内政・外政・危機管理の各実務トップを務めた官邸官僚が参集し、適切な権力行使のための「官邸のトリセツ」を公開する。
内容説明
総理大臣には働いてもらわなければならない。それも最初から、全力で。しかし、巨大タンカーのごとき日本政府を操るにはコツが必要だ。政治家の意思で、霞が関は動かせるのか。そして「本物の有事」に直面した時、政治は自衛隊などの実力部隊をコントロールできるのか。歴代最長の安倍政権で内政・外政・危機管理の各実務トップを務めた官邸官僚が参集し、適切な権力行使のための「官邸のトリセツ」を公開する。
目次
第1章 官邸主導の虚実
第2章 危機管理への対処
第3章 安全保障の司令塔としての官邸
第4章 予算編成、財政、通商問題
第5章 インテリジェンス
第6章 メディアと戦略コミュニケーション
第7章 内閣官房と内閣府の役割分担
著者等紹介
兼原信克[カネハラノブカツ]
1959年生まれ。元内閣官房副長官補(外政担当)
佐々木豊成[ササキトヨナリ]
1953年生まれ。元内閣官房副長官補(内政担当)
曽我豪[ソガタケシ]
1962年生まれ。朝日新聞政治部編集委員
〓見澤將林[タカミザワノブシゲ]
1955年生まれ。元内閣官房副長官補(安全保障・危機管理担当)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
kawa
うえぽん
SGR
Masayuki Shimura
カツ丼