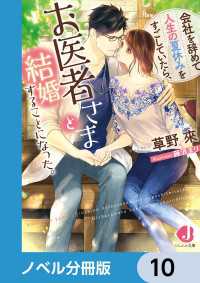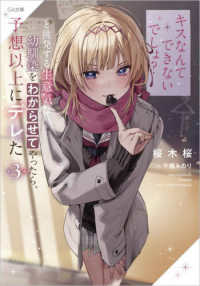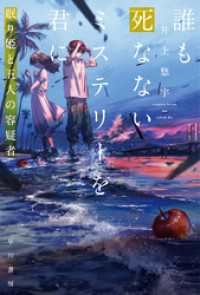内容説明
ある作品を媒介に作家と禅僧が出会い、七年越しの対話が始まった。信心への懐疑、坐禅の先にあるもの、震災とオウム…はたして仏教は、人生のヒントとなるか。実存の根源的危機が迫る時代に、生死の覚悟を問う。
目次
第1章 生命と死の門―二〇一一年一月二十五日(黒衣のダース・ベイダー;ふたつの「サンガ」 ほか)
第2章 坐禅の先にあるもの―二〇一一年一月二十五日(オウムに決定的に欠けているもの;懐疑の訓練 ほか)
断章(道元がたちあらわれるところ(高村薫)
運動する『正法眼蔵』(南直哉) ほか)
第3章 信心への懐疑―二〇一八年九月十三日(「住所不定住職」;「仏教の突破」 ほか)
第4章 生死の覚悟―二〇一八年九月十三日(震災文学の決定版;生死の覚悟 ほか)
著者等紹介
〓村薫[タカムラカオル]
1953年生まれ。作家。90年にデビュー。93年、『マークスの山』で直木賞受賞
南直哉[ミナミジキサイ]
1958年生まれ。禅僧。青森県恐山菩提寺院代、福井県霊泉寺住職。84年に出家。2018年、『超越と実存』で小林秀雄賞受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
KAZOO
107
高村薫さんと曹洞宗の住職で哲学書の著作もある南さんとの対談と小文が掲載されています。お二人ともにそれまで接触がなかったようですが「太陽を曳く馬」の主人公が永福寺にいた当時の南さんにそっくりだと周りの坊さんたちに言われていたそうです。やはり道元や正法眼蔵の話は結構難しい感じを受けました。高村さんの本はほとんど読んでいるので、また最初の著作から再読中です。正法眼蔵は以前途中で放り出した森本和夫さんの「正法眼蔵読解全10巻」を再度挑戦しようという気になりました。2024/08/20
kaoru
74
高村氏と南氏の二度の対談を含む著書。阪神淡路大震災を経験した後13年かけて『太陽を曳く馬』を書いた高村氏、「人が対象を持たずに何かを信じるというのが成り立つとしたらそれは概念としては博打に近い」と言う南氏。真摯過ぎる方々なので一度の読書では到底語れず、両氏の書いた「断章」などに手がかりを探してゆきたい。『太陽を曳く馬』に関する記述も実に興味深い。「『何もかも大丈夫』『ありのままの君でいい』という言葉に対する違和感を大事にして、自己であることの負担に耐え続けるべきだ」と南氏。「苦しい状況を簡単な言葉で⇒ 2021/09/14
道楽モン
48
南直哉氏は、曹洞宗(禅宗のひとつ)の僧侶にして一般啓蒙書から専門書まで著している文筆家。高村薫は、阪神淡路大震災をきっかけとして宗教、とくに仏教へ導かれ、膨大な文献を読み漁り、修行僧を主人公とした『晴子情歌』から始まる福澤彰之シリーズ三部作に結実された。この対談の中心は、仏教の知識や教養を言語で積み上げた両者にとって、肉体的な信仰体験なしに「信じる」ことが可能なのかという問題だ。これは信仰の根本であり、南の立場からすれば非常にスリリングな主題である。初対面からスタートした対談だが、強い意気投合で終わる。2024/11/19
ぐうぐう
40
作家と禅僧の対話。高村薫は「およそ宗教と名のつくものにひざまずくことができない」人間であると自身を分析しているが、そんな高村が阪神淡路大震災を機に、仏教と出会う。ただ、事は簡単ではない。「信心」という壁が、彼女に立ちはだかるのだ。仏教の持つ言葉に近付くことはできても、仏を信じることができない。そんな彼女が、信心を持つことの困難さを否定しない禅僧・南直哉との対話の中で、仏教とは、宗教とは、信心とは、あるいは震災やオウム真理教といった社会問題までを語り尽くす。(つづく)2019/05/29
yumiha
38
岸本佐知子が感性の人ならば、髙村薫は理性の人だと思ふ。多読と綿密な取材で思考を深める髙村薫と禅僧の南直哉師との対談書。同居人の死に悔いを残していたので、いろいろな本を読みながら①何事も成就する途中で死は訪れる②凡人(私のこと)には悟りを得ての死などありえない、と思い至って気持ちが少し楽になったことを思い出させてさせてくれた本書。なんと南直哉師は、宗教家であろうともほんまもんの悟りは訪れず、その手前の準悟り(my造語)を問い続け更新してゆくのだと言う。それなら凡人には到底無理だね、と再確認できた。2024/11/29