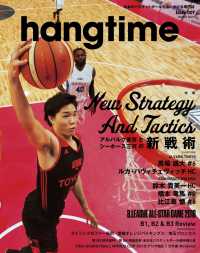出版社内容情報
インバウンド・ツーリズムで里山を再生せよ! 「逆張りの戦略ストーリー」を大公開。
内容説明
岐阜県北部の飛騨に、世界80ヶ国から毎年数千人の外国人旅行者を集める人気ツアーがある。その最大の売りは「なにげない里山の日常」だ。小学生のランドセル姿に、カエルの鳴き声の拡がる田んぼに、蕎麦畑の中に立つ古民家に、外国人は感動する。なぜ、なにもない日本の田舎が「宝の山」になりうるのか。地域の課題にインバウンド・ツーリズムで解決を図った「逆張りの戦略ストーリー」を大公開。
目次
第1章 グローバルカンパニーと世界放浪を経て飛騨へ
第2章 日本の田舎は世界に通じる
第3章 タダの景色でお金を稼ごう
第4章 大変だけど楽しい田舎暮らし
第5章 企業経営の手法を地域経営に
第6章 日本と世界の田舎をクールに
著者等紹介
山田拓[ヤマダタク]
1975(昭和50)年奈良県生まれ。株式会社美ら地球代表取締役。横浜国立大学大学院工学研究科修了。コンサルティング会社勤務の後、夫婦で五百二十五日間の世界放浪を経験。2007年、飛騨市観光協会の戦略アドバイザーに就任し「美ら地球」を創設(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
at-sushi@進め進め魂ごと
50
豊富な海外経験の中で、日本の何処にでもある農村風景の価値を再発見し、「旅行商品」として成功させた著者。以前から「着地型観光」が謳われていながら、国内で殆ど定着していないのは、そもそも日本に「ツーリズム」文化が無いから、というのは納得。日本人相手に、東京近郊にも無いことはない農村風景が刺さるとは思えないし、それをゆっくり楽しむ長期休暇制度も無い以上、「ツーリズム」商品を作るうえでは、やはりインバウンドをターゲットにする以外無い気がする。(いつ復活するのか不明だが)2022/02/24
けんとまん1007
33
いわゆる田舎に近い環境に暮らす者として、興味深く読んだ。中でも書かれているとおり、地域での人間関係は、重層的であり、距離感もとても近い部分が多い。それを含め、日常の暮らし自体が、とても価値のあるもので、かけがえのないものであると思っている。ただ、その中にいるお、そこに気づかないことが多いのも事実。そこに立脚するところから、この1冊は始まる。ものごとを、それまでにないことを始める場合、いろんなことが立ちはだかる。それにどう対峙するのかで決まる。自分が暮らすところから、そう遠くない場所というの感慨深い。2018/04/29
Kentaro
26
飛騨古川の市街地の古い町並みと農村部、両方の魅力を楽しむには自転車を使うのが効率的だ。しかも、自転車なら、ちょっと立ち止まって地域住民と交流するのがたやすい。こうして飛騨里山サイクリングが誕生。ゲストには欧米系の観光客が多い。彼らの生活空間に水田はない。人は見慣れぬ風景に感動を覚えるものだ。田んぼの中のアマガエルさえ興味深い対象となる。そこで生活する人々にとっては何の変哲もない風景だが、それが日常でない人たちから見れば、橋の上から眺める川の流れや作物がなっている風景でさえ、感動に値するものとなるといえる。2019/04/02
roatsu
26
今後の観光施策や地方再生における一つの典型例を実現したパイオニアとして、多くの試練と試行錯誤を経た無二の体験とそこから得た知恵を読者に共有する一冊。仕事、そして人生というプロジェクトのマネジメントの手本としても素晴らしい。読めば多くの発見が得られる必読の書だと思う。国土保全上も都市生活からの田園回帰は重要だが、その諸々の現実に関する体験した者にしか語り得ない逸話の数々は貴重。緩慢な死を座して待つのみの状況でも固定観念や既定路線を手放さない現代日本人の在り様についても改めて考えさせられた。ともあれ、苦労や苦2018/06/01
おせきはん
17
岐阜県飛騨市で顧客の8割が外国人を占めるサイクリングツアーを行っている著者の経験がまとめられています。飛騨市への移住、資金調達、人材確保など多くの苦労を乗り越え、地元の方々の協力も得ながら「何気ない日常」の魅力を外国人に伝え、支持されるようになった著者の行動力に感銘を受けました。ガイドと小回りのきく自転車が、飛騨古川の景色と住民の魅力をうまく引き出しています。地域活性化を支援する人は多いもののプレーヤーが少ないという指摘には、支援する側の者として考えさせられました。2018/01/20