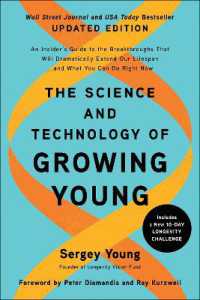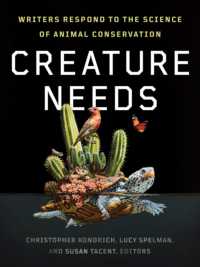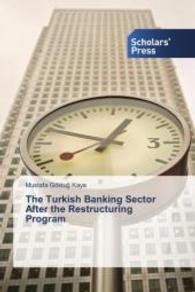内容説明
茶を「礼儀作法を学ぶもの」「花嫁修業のため」で片付けるのはもったいない。本来の茶の湯は、視覚、聴覚、触覚、味覚、嗅覚の全領域を駆使する生活文化の総合芸術なのだ。なぜ戦国武将たちが茶に熱狂したのか。なぜ千利休は豊臣秀吉に睨まれたのか。なぜ茶碗を回さなくてはいけないのか。死屍累々の歴史、作法のロジック、道具の愉しみ―利休の末裔、武者小路千家の若き異才の茶人が語る。新しい茶の湯論がここに。
目次
第1章 誤解される茶の湯
第2章 茶の湯の歴史を駆け足で
第3章 茶家に生まれて
第4章 利休とは何ものか
第5章 茶席に呼ばれたら
第6章 茶道具エッセンシャル
第7章 深遠なる茶室
第8章 茶事はコミュニケーション
著者等紹介
千宗屋[センソウオク]
1975(昭和50)年京都生まれ。本名は千方可。茶道三千家の一つ、武者小路千家十五代次期家元として2003年、後嗣号「宗屋」を襲名。慶應義塾大学大学院修士課程修了(中世日本絵画史)。2008年、文化庁文化交流使に。茶道具のみならず古美術、現代アートにも造詣が深い(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
こきよ
77
現代に於いては茶も多くの流派に分かれてはいるが元を辿れば珠光、紹鴎、利休に行き着く。武者小路千家の次期家元という立場でありながら客観的に総体を俯瞰できる氏の様な若き茶人は貴重な存在なのではないか。他の著作も読んだがこの宗屋氏…かなりの数寄者である。2015/08/09
ume 改め saryo
25
武者小路千家 15代家元は博学ですね(^^) そして自分に厳しい方なんですね。 本として面白く読ませるというより、事実に基づいた考証なのかな? それでも楽しく読める部分も多く、ためになるお話もあり満腹です(笑)(^^)/ 2014/01/17
ぐっちー
18
流派にこだわらず、茶道とは何かを平易な言葉とユーモアを交えながら語りかける入門書。堅苦しい作法で、敷居がやたらと高いと感じられるお茶。しかし本来的な意義をあらゆる方向から示してくれる。パフォーミングアートとして。主客が同期する体感の場として。手前を、「心を形にして見せていくプロセス」とし、「型の中にエゴを収めてみるとぶれやすく不安定な心」を「客観的に見直して、そのぶれを少しでも止めていく」ということに瞠目。2016/04/28
calaf
16
茶?三回回すのでしたっけ...というぐらいしか知らない私には、ちょっと難しすぎたかも (大汗) でも、一つ分かった事が。茶会って、お茶だけではなくて料理まで出てくるものなのですか!!!お菓子ぐらいは出るかもという気はしていたのですが、デフォルトで懐石料理があるとは...うーむ...余計にハードルが上がった気がする...2013/03/15
rena
11
茶道に詳しくなはいけれどとても茶について歴史や文化、三千家の特徴が分かりやすく書いてあり、だれが読んでも茶文化に関心を持つのではないかと思う。利休の末裔 の著者。でも茶は、最初は、決してわびさびではなくて、ハイになる薬、飲み比べの テイスティングで遊んだり、広間に唐物の宝を飾り立てて鑑賞したりが日本の最初の茶だったとか。応仁の乱で荒廃して必然座敷が狭くなったらしい。自分の本ではないので、購入して手元に置きたい~。独茶で 自分用にお茶立てるもの大切というので、今度自己流茶をたててみよう。2016/06/19