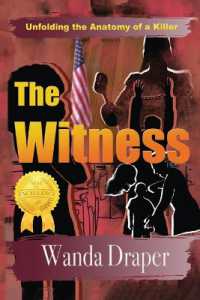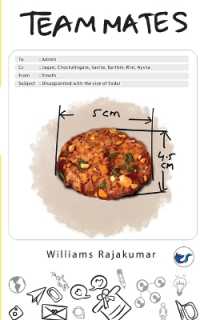出版社内容情報
「東大こそは諸悪の根源!」――批判者たちの大義名分とは? 国家のエリート養成機関として設立された「東大」。最高学府の一極集中に対し、昂然と反旗を翻した教育者・思想家がいた。慶應義塾、早稲田、京大、一橋、同志社、法律学校や大正自由教育を源流とする私立大学、さらには労働運動家、右翼まで……彼らが掲げた「反・東大」の論理とは?「学力」とは何かを問う異形の思想史。
内容説明
「東大こそは諸悪の根源!」―批判者たちの大義名分とは?国家のエリート養成機関として設立された「東大」。最高学府の一極集中に対し、昂然と反旗を翻した教育者・思想家がいた。慶應義塾、早稲田、京大、一橋、同志社、法律学校や大正自由教育を源流とする私立大学、さらには労働運動家、右翼まで…彼らが掲げた「反・東大」の論理とは?「学力」とは何かを問う異形の思想史。
目次
第1章 「官尊民卑」の打破―慶應義塾・福澤諭吉の戦い
第2章 「民衆」の中へ―レジャーとモラトリアムの早稲田大学
第3章 「帝大特権」を〓奪せよ―私立法律学校の試験制度改正運動
第4章 「学問」で東大を凌駕する―一橋大学の自負と倒錯
第5章 「詰め込み教育」からの転換―同志社と私立七年制高校
第6章 「ライバル東大」への対抗心―京都大学の空回り
第7章 「知識階級」を排斥せよ―労働運動における反・東大
第8章 「凶逆思想」の元凶―右翼に狙われた東大法学部
終章「反・東大」のゆくえ―東大の「解体」と「自己変革」
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
KAZOO
78
最近テレビや出版物で東大の名をかぶせたりすると視聴率が上がったり売れるということの一環で出版されたと思ってしまいます。ただ東大の歴史やその役割についてはかなりよく調べられていると感じました。ただ官僚養成所的な教育機関もそれなりに存在意義があったのでしょう。官学でも少し違う京都大学やそのほかの私学の役割をただ「反・東大」という観点だけではなく、もう少し違った観点から書かれてもよかった気がします。2024/12/14
koji
21
本書は、書名に「東大」は入っているが、単に学歴・教養論ではなく、明治維新後の日本が欧米近代国家に追いつく「国づくりのかたち」を官主導の効率至上主義に求めたことを説いた思想史と感じました。とりわけ8割以上を占める明治から昭和前期までの章は、東大側、反東大側の互いの主張が分かり易く記述され、とても読み応えがありました。結局、いかなる批判にも耐えた東大主導の国づくりはうまくいったのか。結論だけ言えば否でしょう。大きな歪み(軍台頭、敗戦)をうみました。良書ですが一つ注文。戦後の自己変革がサラッとしすぎ。ぜひ続編を2024/10/13
バーニング
6
自分が早稲田出身なので慶應、早稲田のくだりを面白く読んだ。それ以外だと一橋のくだりも面白い。東大に吸収統合される可能性を常に孕みながら東大とは違う大学として地位を築いてきた歴史が詳しく紹介されている。2025/02/27
n_2_d_6_m_0_p_1
4
日本の学歴コンプレックス・学歴厨史としても読める。たまたま東大王が最終回を迎えた週に読んだのだが、あとがきによると当番組が執筆動機の一つだった模様。今さら東大を冠してクイズ番組なんてやる意味なんかあるのかと冷ややかに見ていたのだが、なるほど、そういう効果もあったのかと、終わってから気付かされることとなった。2024/09/21
たいたいぶん
3
東大がなぜ日本で一番となっているのか、それに抗った京都、一橋や早慶などのストーリーを記したもの。 個人的には1910年代後半の私学の勃興が関心に残った。成城は設立当初生徒の自主性を尊重した学風をテーマにして設立したという歴史は普通に勉強になったし、戦前の帝大特権には驚きだった。また福沢諭吉が「貧乏人にはそれ相応の環境を」と言ったことにも、学問のすゝめとは... さらに先の私立高校の勃興でも言及されたように、一度の筆記試験で先の人生が決まってしまうこと、そして人間性より暗記力が求められる今の構図も要改善かも2025/08/06