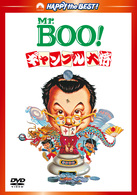出版社内容情報
太平洋戦争を戦い抜いた日本海軍の主力戦闘機・ゼロ戦。栄光と悲惨に満ちた「零戦神話」をクールに検証し、諸元と用兵の両面から真の実力を明らかにする。
内容説明
20mm機銃の弾道は曲がっていたか?最初は無敵だったのか?防御軽視は本当か?撃墜王の腕前は重要か?最期は特攻機用だったのか?初期の栄光から激闘の珊瑚海・ミッドウェイ海戦、南太平洋の消耗戦をへて、マリアナ・レイテ、本土防空戦までの推移を追いながら、飛行性能だけでなく編隊・戦術などの用兵面を検証し、全く新しい零戦像を提示する。
目次
序章 零戦に関する基礎知識
第1章 脇役だった艦上戦闘機―零戦の生い立ち
第2章 性能データにない強み―試作から初陣まで
第3章 内包された弱点―初期不良と改良
第4章 攻勢の優位―栄光の時代
第5章 米軍の新戦法―激闘の時代
第6章 戦果確認の落とし穴―ガダルカナル
第7章 直掩か空中戦か―黄昏の時代
第8章 圧倒的劣勢の中で―レイテから終戦
おわりに―勝敗を分けたもの
著者等紹介
清水政彦[シミズマサヒコ]
弁護士。昭和54年生まれ。東大経済学部卒。金融法務の傍ら、航空機と戦史の研究に励む(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
文章で飯を食う
12
読書後に著者が昭和54年生まれと気づいて、びっくり。著者は零戦の戦果は性能の差では無く運用の差だと言う。確かに著者の描く個々の戦況は、状況や運不運や天気の要素が強く、なかなか用兵者の思ったようには行かない。そんな中、日本が最後までパイロットの養成が追いつかないと、嘆いている時に、アメリカは素人パイロットでどうやって勝つかと、発想を変えている。現代にもつながっている事だろう。日本はたまたま勝つが、アメリカは勝ちに行くんだな。2016/03/19
モモのすけ
12
「零戦と米軍機の勝敗を分けた最大の要因の一つが、日米両軍の『総力戦』に対する覚悟の差と、その差から派生する戦術・空中指揮に対する工夫の差であったように思われる」2013/07/28
ヴァン
8
ゼロ戦をスーパー兵器に祭り上げるのではなく、かといって、貶めるのでもない、読んで納得のできる中庸な分析になっている。同じ工業生産品が一万機以上も産み出された事実は戦中においての日本の技術的成果と言っても過言ではない。日本は負けたけれども、その技術は今度は自動車生産に活かされ、かつての戦勝国を席巻する。2021/10/22
Toska
6
肯定的なものも否定的なものもひっくるめて、零戦神話を問い直す意欲的な試み。零戦そのものの性能もさることながら、兵器の実績と評判は戦局に左右される部分が大きいことを再認識した。また、これは固有の欠点とは言い難いのかもしれないが、射撃教育の不徹底は重大な禍根を残したように感じる。弾を当てたつもりが当たっていなかったというのでは…ノモンハンで戦ったソ連のパイロットも、「日本の戦闘機乗りの技量は優れているが、遠くから撃ちすぎる」との評価を残しており、意外と古くからあった問題なのかもしれない。2021/06/05
tora
5
零戦に対し新しい認識を与える内容が多い。他の本でも時々高アスペクト比の21型22型の緩慢なロールレートに関する記述は見たことがあるが、ここまで詳細に説明している本に出会うのは初めてである。20mmの弾道や零戦の機体強度については、これまで言い伝えられてきたことと全く異なる見解である。その上で零戦や敵機の長所短所を説明している点は興味深い。多少強引で想像によって書いたような箇所が見られ、資料不足・説得力不足な感も否めないが、若い著者がこれまで一般的に語られてきた零戦観に異論を唱えたことには感心せざるを得ない2009/11/07