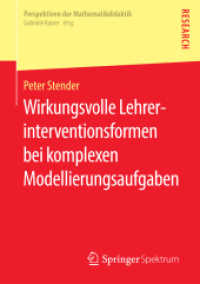内容説明
量子場理論―それは量子力学の完成形である。物理学専攻の大学院生にとってさえ理解が容易ではないこの超難解な理論を、本書はあくまでも一般読者のために解説してみせる。20世紀の天才科学者たちは、いかにして「物質とは何か」という謎を解き明かしたのか?その思考の筋道が文系人間にも理解できる画期的な一冊。
目次
序章 原子と場―19世紀物理学の到達点
第1章 粒子としての光―アインシュタイン
第2章 原子はなぜ崩壊しないのか―ボーア
第3章 波動力学の興亡―ド・ブロイとシュレディンガー
第4章 もう1つの道―ハイゼンベルク・ボルン・ヨルダン
第5章 光の場―ディラック
第6章 電子の海―ディラックとパウリ
第7章 量子場の理論―ヨルダン・パウリ・ハイゼンベルク
第8章 くりこみの処方箋―朝永・シュウィンガー・ファインマン
終章 標準模型―20世紀物理学の到達点
著者等紹介
吉田伸夫[ヨシダノブオ]
1956年、三重県生まれ。東京大学理学部物理学科卒業、同大学院博士課程修了。理学博士。専攻は素粒子論(量子色力学)。東海大学、明海大学で非常勤講師をつとめながら、科学哲学や科学史をはじめ幅ひろい分野で研究を行なっている(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
俊介
15
量子力学が完成されたと言われるのが1926年。だが、物理学者にとっての本当の戦いはそこからだったらしい。「量子場の理論」というものを完成させないと、あらゆる物事を説明できるような理論としては、未完成だったからだ。「究極の理論」を求めるのはもう科学者の性なのだろう。当然、中身は超絶難解だ。とりあえず好奇心で読んでみたけど、意味不明。それでも本書は、理論の中身の解説だけでなく、科学者たちが「究極の理論」を追い求め、いかに悪戦苦闘してきたかの足跡を辿る書でもある。一流学者たちが煩悶苦悩する様子は壮絶、見ものだ。2021/08/26
fseigojp
9
懇切丁寧に20世紀物理学を解説2015/07/17
mstr_kk
8
半端な知識しかない僕のような文系科学ファンには、かなり難しい、けど、超面白い本でした。というか、世界観をひっくり返されました。今まで何となく、量子論や素粒子論の概要はつかんでいるつもりだったんですが、いろんなレベルで間違ってました。特に、「素粒子の標準模型は、量子場の理論としてのヤン=ミルズ理論からできている」ということが、何を意味するのか。……僕は今まで、「素粒子っていう粒がある(それは波の性質ももつ)」と考えてました。これ、間違いだったんですね。場が振動するのが粒子みたいに見えるだけなんですね。2019/09/23
mstr_kk
4
再読。同じ著者の問題意識が研ぎ澄まされた新刊『量子で読み解く生命・宇宙・時間』を読んだため、前よりも論旨をつかみやすかったです。20世紀の量子論関係の物理学史として、めちゃくちゃ秀逸で面白いです。難しいところは多々ありますが。2022/06/19
大道寺
4
東洋思想を学んでいると量子力学は避けては通れない道のように思われる。逆に物理学者たちも東洋思想に着想を得たという話もある。量子力学に興味をもったのはそんなところから。「はじめに」にあるように私もまた不確定性原理やシュレディンガーの猫ばかりを取り上げて量子力学すごいねと言い合っている一般人の一人である。しかし哲学の本に書いてある都合の良い量子力学解釈しか知らないというのはこの先思索を深めていく中で危険であると考えて本書に水先案内人となってもらうことにした。(続く)2010/08/21
-

- 電子書籍
- 異世界女子、精霊の愛し子になる(7) …