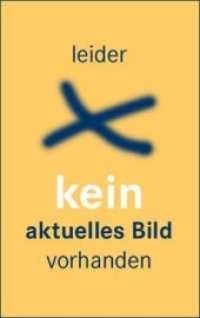内容説明
性が入れ替わったまま成長する男女を描いた、異色の王朝文学『とりかへばや物語』。かつて「淫猥」と評されたこともあった物語には、「性の境界」をめぐる深いテーマが隠されていた。男らしさと女らしさ、自我とエロス、性変換と両性具有―深層心理学の立場から、ジェンダーと性愛の謎を解き明かすスリリングな評論。河合隼雄が遺した名著、選書版で登場。
目次
第1章 なぜ『とりかへばや』か
第2章 『とりかへばや』の物語
第3章 男性と女性
第4章 内なる異性
第5章 美と愛
第6章 物語の構造
著者等紹介
河合隼雄[カワイハヤオ]
1928年兵庫県生まれ。心理学者・心理療法家。京都大学理学部数学科卒業。スイスのユング研究所への留学等を経て、日本におけるユング心理学の第一人者となる。京都大学名誉教授、国際日本文化研究センター所長、文化庁長官を歴任。『昔話と日本人の心』で大佛次郎賞、『明恵 夢を生きる』で新潮学芸賞受賞。2007年没(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ばんだねいっぺい
33
国文学では、評価が分かれる「とりかへばや物語」を心理療法的視点で読み解く。中将のトリックスターぶりに驚嘆したし、類似の物語として紹介される山本周五郎の「菊千代抄」にもこころ掴まれた。結末に見えるものは、壮大な物語の始まりといったように、男と女、アニマとアニムスが人間ドラマを織り成す凄まじいパワーなんだということに畏怖と面映ゆさを感じた。2019/01/06
ほよじー
15
★★★「とりかへばや物語」は男ー女の軸について考えさせられる物語である。人間は生まれてくる時、男になるか女になるかを自分で「選ぶ」のではなく、本人の意思とは無関係に運命的に決定されている。そして「男らしい」「女らしい」等の固定観念によって社会的に行動が縛られてしまう。混沌に秩序を与えるためには、男女、善悪、優劣、精神・身体などの二分法的思考が有効であると考えられてきたが、果たしてそうだろうか。例えば心身症は精神と身体の二分法的思考に反逆するものである。二分法的秩序を一度打ち壊してみることが有効という。2016/10/15
roughfractus02
9
天狗の仕業によって男として育てられた姉と女として育てられた弟という日本古典の稀有な物語設定を、著者はユング心理学での男性の中にある女性像アニマ(魂)と女性の中にある男性像アニムス(知性)という社会的性差として解釈し、生物学的性差とは別の社会的なジェンダーアイデンティティを取り出し、人間の両性具有的な心理という設定から捉え直す。本書は、未分化の無意識が性差に分岐して自我意識を持ち、個人から社会へ拡張する過程にアニマ/アニムスのいくつかの可能的段階があり、無意識と意識が対話が個性化の過程を作ることを示唆する。2023/01/23
詠月
8
男ー女、善ー悪、優ー劣…二分法によって縛られた思考は、男らしさ、女らしさの規律がなければ社会秩序を維持出来ないと判断し、秩序の為の道徳をうみだしました。sexーidentityは深い問題で、アニマ、アニムスの話は難しかったです。ユング先生も難しいです。2013/08/09
もち
6
やや古いと感じる部分もあったが、おもしろく読んだ。日本と中国の違いを改めて噛みしめた。2017/07/20
-

- 電子書籍
- 魔法使いと赤のピルグリム【分冊版】 1…
-

- 電子書籍
- 振り向けばいつも〈パリから来た恋人Ⅱ〉…