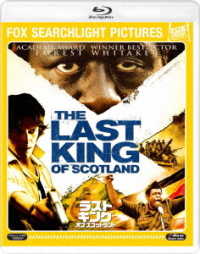内容説明
茶人として茶の湯を総合芸術に高め、作庭家として日本の庭の新しいスタイルを確立し、作事奉行として禁裏・幕府の建造物を担当。まさに、八面六臂の活躍を果たした小堀遠州。彼の愛した“綺麗さび”の世界とは何か?この万能の達人の全貌に迫る。
目次
第1章 泰平の世の茶の湯を拓く―茶人としての遠州(わび・カブキ・きれい―小堀遠州の茶の湯の系譜)
第2章 自然と人工を調和させる名手―建築家・作庭家としての遠州(江戸の“アートディレクター”小堀遠州の建築術;四通八達の庭づくり)
第3章 今に伝える「綺麗さび」のこころ―総合芸術家としての遠州(思いやりの美、「綺麗さび」)
第4章 武士から凄腕テクノクラートへ―公人としての遠州(小堀遠州とその周辺)
全国遠州ゆかりの地を巡る
小堀遠州略年譜―「平穏にして豊かなる生涯」
著者等紹介
小堀宗実[コボリソウジツ]
1956年遠州茶道宗家に生まれる。遠州茶道宗家、十三世家元不傳庵(ふでんあん)。学習院大学卒業後、大徳寺派桂徳禅院にて禅の修行を積む。1983年、副家元に就任。2001年、十三世家元を継承する
熊倉功夫[クマクライサオ]
1943年東京生まれ。東京教育大学文学部日本史学科卒業。日本文化史専攻。文学博士。京都大学人文科学研究所講師、筑波大学教授、国立民族学博物館教授を経て、(財)林原美術館館長、国立民族学博物館名誉教授、総合研究大学院大学名誉教授。茶道史、寛永文化のほかに、日本の料理文化史、民芸運動など幅広く研究
磯崎新[イソザキアラタ]
1931年生まれ。建築家。磯崎新アトリエ代表。東京大学、UCLA、ハーヴァード大学、コロンビア大学など国内外の客員教授を務める。英国RIBAゴールドメダルなど受賞。主な作品に「大分県立図書館」「群馬県立近代美術館」「ロス・アンジェルス現代美術館」「セラミックパークMINO」「有時庵」「トリノ・パラホッケー」
龍居竹之介[タツイタケノスケ]
1931年東京生まれ。早稲田大学卒業後、日刊スポーツ新聞社文化部記者を経て、1972年より(有)龍居庭園研究所所長。1990年、文化庁文化財保護審議会専門委員。2004年より(社)日本庭園協会会長。2005年より、創造学園大学客員教授。古庭園の修復整備とともに、庭園の啓蒙活動にも従事(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
クラムボン
クレリック
T
さんとのれ
Osamu