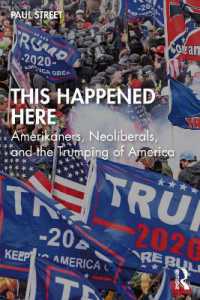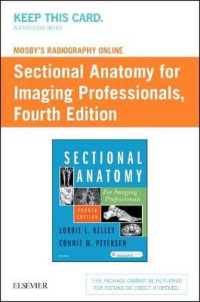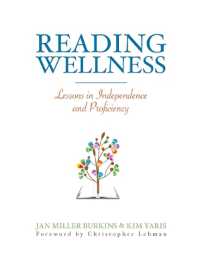内容説明
誰にも気兼ねなく、ある日は終日読書三昧、またある日は浅草で過ごし夜半に帰宅。自宅の手軽な自炊には、七輪を部屋に持ち込んで…。そして孤独も老いも死も、さらりと語る独居の達人。吝嗇だ奇行だと陰口きかれても気侭に生きた後半生。
目次
第1章 ひとり暮らしの賑わい(荷風のひとり暮らし遍歴;身のおきどころ;金と時間の使い方 ほか)
第2章 食の歓び、自炊の愉しみ(荷風の食べもの遍歴;好物・鰻の蒲焼き、そしてお歌;茶筒に残る葛粉 ほか)
第3章 散人、晩年に愛した街(川を渡って浅草へ;心癒された市川の風景)
第4章 好んだ季節の花々
著者等紹介
永井永光[ナガイヒサミツ]
1932年東京生まれ。父・大島一雄(杵屋五叟)は荷風の従兄弟にあたる。1944年、永井荷風・壮吉の養子となる。荷風没後、家族と共に八幡の荷風旧宅に移り、家屋、遺品を守り続けている。1956年からバーを経営
水野恵美子[ミズノエミコ]
1967年福島生まれ。出版社を経てフリーランス編集者・ライター。食と暮らしをテーマに雑誌・書籍で活動。特に人物を題材に、「食」から見えてくるその人間像を描いている
坂本真典[サカモトマサフミ]
1940年旧満州チチハル生まれ。出版社写真部を経て独立(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ワッピー
24
荷風のビジュアルムック本。「断腸亭日乗」に描かれた荷風の愛用品や暮らしの様子を写真とともに養子の永光氏が解説。生活を共にした永光氏の見た等身大の荷風も興味深く、しばらく離れていた荷風界を再訪する縁として、大いに楽しみました。本書のお得なところとしては、写真の他、中編「ぬれずろ草紙」の抜粋が掲載されているところ。これは荷風が昭和23年頃に「断腸亭~」で言及しているものの、全集には収録されていない春本で、進駐軍と女性との交渉を戦争未亡人の視点から描いたものです。荷風の生涯をつかむ手軽な入門書としてはオススメ。2019/05/13
ステビア
10
まさに独身貴族。2015/08/26
すたれがみのきれはし
6
荷風の愛用していた遺品などを中心とした写真と、ひとり暮らしの様子を養子(と言っても一緒に生活した期間はごくわずか)の永井永光氏が語っています。良家の生まれなのにとても偏屈でドケチ、ですがいわゆる下層に身を置く女性や下町をこよなく愛した人。荷風の最期は今で言う孤独死ですが、孤独を愛していた荷風は寧ろあの死に方を望んでいたのだろうな、とも思いました。 しかしぬれずろ草紙、官能小説かというほどのエロスっぷりでびっくりしました。永光氏も二度と公開しない、と語っているのでこの本以外でお目にかかれる機会はなさそう。2019/06/25
屋根裏部屋のふくろう🦉
6
この書籍は荷風を知る教科書になったので、小生にとって大切な保存版。人嫌いな荷風は一人で食事をする。尾張屋本店では食べている姿がある追っかけ青年によって撮影された。それがいい味を出している。荷風の顔よりも、店の暖簾の奥でカメラを覗き見しているお店の人の表情がいい。いつも決まった時間に決まった席、注文せずに腰を下ろしてかしわ南蛮が来るのを黙って待つのが荷風の必勝パターン。店では荷風の姿が見えると作り始めた。この本以来、なんと言うこともなく小生は小さめのドクターバッグを携行するやうになった。2018/03/03
かわかみ
5
「断腸亭日乗」をベースに二度の結婚後、余生を一人で過ごした荷風の暮らしぶりを、彼が好んだ道具・食・街・花を紹介しながら探った書。荷風の遺品など写真が多く掲載されている。鴨長明は出世を親族に邪魔されて世をはかなみ隠棲したが、荷風は一人暮らしというだけで、美味いものを食べ、劇場の踊り子たちにちょっかいを出して人生を楽しんでいた。ただし、誰にも最期を看取られずに一人で往生することを望み、実際にそのとおりの辞世となった。文化勲章の年金でもっと踊り子たちと遊べると思ったら逆に敬遠された話は面白い。2023/05/02