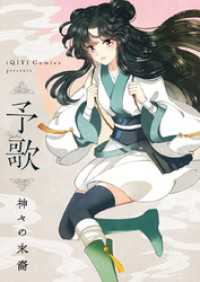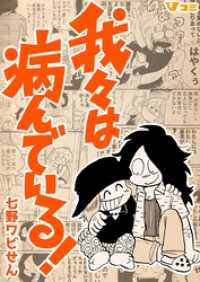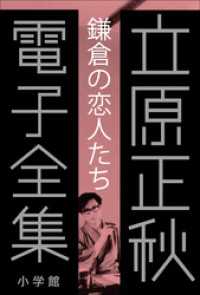内容説明
合言葉は「世紀末」―「最期の時が近づいた」時、画家たちは、いかなる想像力を発揮するのだろうか?世紀末の物語絵は、なんらかの逸話を物語ると同時に作者自身の内部をも映していき、そして物語らぬようになる。さまざまなイメージに、さまざまなシンボルが託され、錯綜していく。新たな世紀末たる現在、「エロス」「愛と死」「信仰と秘儀」など18のキーワードで、世紀末の闇を解き明かしてゆく…。
目次
序章 物語る絵、物語らぬ絵
第1章 生贄にされる男たち
第2章 苦悶する自我
第3章 死、そして愛
第4章 夕闇に浮かぶ異形
第5章 不安と絶望
第6章 彼方へ
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
めがねまる
23
闇、異形、死、不安と絶望、先の見えない世紀末だからこそ花開いた幻想的な美しい絵画群が世紀末美術だ。画家たちは自らの境遇やメッセージを、直裁にではなく婉曲に、美に包んで発表した。「物語らない物語絵」は見るものを苛立たせ、かろうじてシュルレアリスムに命脈を保ったそうだが、だんだん何が本当で何が嘘かわからなくなっていく不確かな時代にはこういった、生と死の境界線上にある美術が輝いて見える時ではないだろうか。この中ではクノップフ、シュトック、ホイッスラーが気に入った。特にシュトックの「原罪」は素晴らしく不気味だ。2017/06/28
内島菫
21
最も気に入ったのは、ラッセルの「私が建てたのは、この偉大なバビロンではないのか」。本書でも、「世紀末の秘儀や信仰は多くの場合、黒と白のいずれとも定めがたい不思議空間や不思議時間ともいうべき世界を見せる。その系列の作品の中で最も美しく神秘的な例の一つ」と紹介されている。「私が建てたのは、この偉大なバビロンではないのか」は、イスラエルに災いをもたらした罪で神に動物に変えられてしまう直前にネブカドネザルがつぶやいたという言葉。2018/03/13
春ドーナツ
8
図書館から酷寒の喫茶店に向かう途中、局地的ゲリラ豪雨と遭遇した。予定では図書館滞在時刻5分だったのが、30分以上ぶらぶらしたことが敗因である。魔の巣窟ですね。雨雫の路面からの跳ね返りがウエスト近く。傘役立たず。喫茶店で本書を読みながら、脚を組み替えるたび、「ガリガリ」音がしたけれど、氷結したのか。クリムトの「ダナエ」に惚れ込む。そう言えば、「世紀末」をもう味わうことができない。ある本でアメリカの「人口冬眠請負サービス業」に関する本を読んだが、まだ営業中なのだろうか。2017/07/24
nizimasu
5
いきなり表紙からモローのユピテルに、見開きがフレデリックの流れ(多分、会田誠の源流)みたいなインパクトの連続。よくよく考えると自分が小さい頃に遊んでいたオカルト趣味的な要素の原点がこれらの作品に触れるとよくわかる。退廃美とエロスにタナトスが交錯してヤバい世界。深入りは現金だけど、何とも言えない世界観についつい引き込まれてしまいました。まだまだ知りたい世界だなあ2014/02/14
takakomama
4
世紀末美術がどういうものか、定義がわかりました。自我や愛と死、不安と絶望などの闇が深いですね。モロー、クリムト、ラファエル前派など、今年は世紀末美術の美術展をたくさん観ています。2019/06/30