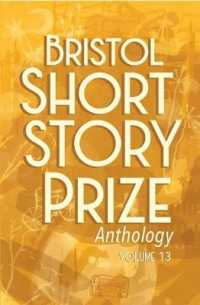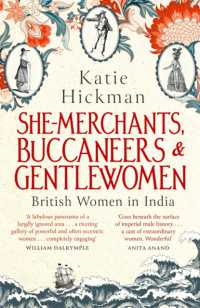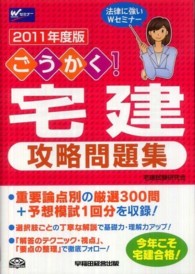内容説明
日本と西欧、死に対する考え方。火葬ののち遺鏡をバラ園に―西欧の新しい方法と献体、臓器移植への影響を語る。
目次
第1部 日本とイギリス
第2部 家族墓所の伝統(火葬の社会的風土;ヨーロッパの土葬家族墓所)
第3部 変革の時代(芸術としての日本の火葬;両極分解するヨーロッパの火葬)
第4部 あたらしい死生観(ヨーロッパの献体;日本の献体と臓器移植;個体死確認の歴史)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
アナクマ
30
火葬の歴史は思ったより少なめ。日欧の文化比較に重き。90年刊行時点でお骨のゆくえを案じている。葬送はどうなるのだろう。というか、私はどうするのだろう。死者への想いの国ごとの違い/共通点にも思いを進めさせられた(海外の墓所を眺めるだけでは解らないこと)。◉1章、江戸明治火葬。2章、死後のすみかを共にしたい家族墓所→収骨地下埋葬。4章、あたらしい死生観(献体臓器移植個体死確認)◉(p.71)戦後、座棺から寝棺へ。焼きすぎても焼きたらなくともいけない、日本ならではの芸術としての火葬の誕生。喉仏は第二頸椎。2019/10/02
印度 洋一郎
4
西欧やアメリカに比べると、極端に高い日本の火葬率。江戸時代までは土葬並存だったのに、何故火葬中心になったのか?という分析から始まり、イギリスやドイツの近代火葬の変遷や火葬場の実態、そして何故か献体や臓器移植まで言及。日本の火葬は「家族墓への執着」を明治政府の政策が後押しする形で定着したのではないか、というのが著者の見立てだ。そして、反キリスト教的主知主義を背景にして、遺灰をバラ園に散布してしまうイギリス式火葬や、火葬場の無い地域の遺体が持ち込まれ、遺灰を書留郵便で返送するドイツなど海外葬儀事情も興味深い2017/05/13
東雲
3
卒業論文の参考文献。日本と欧米諸国の火葬及び墓制について比較したもの。学術書ではないが統計などが多く客観性が高い。2016/01/18
mimm
1
世界の火葬の歴史や文化かなーとか思ったら、近代の火葬に関して、ヨーロッパと日本の比較でした。ま、宗教的側面は多大にあるだろーなーとか(確か審判の日に墓から起き上がる、だったか)抵抗に関しては容易に想像もつきましたが、吹っ切れると散骨まで行くか!24年前の本なので、多少は今と違っている部分も出てきてると思いますが、焼却時における死体の窃盗、紛失的事件を数年前の新聞記事やらノンフィクション本で読んだので、こんな雑じゃね、と納得。2014/01/26
MIRACLE
1
現代ヨーロッパの葬式事情について、火葬との関連をもとに、紹介した本。献体と臓器移植、死の判定についても、とりあげている。火葬についての分析は断片的で、現地の火葬場・墓地の取材内容が中心だった(しかも、こまかい数字の羅列がおおくて、読みにくい)。現在も、ヨーロッパでは、土葬がかなり残っている。したがって、本書から「火葬の文化」について学ぶことは、無理があるのではなかろうか。2014/08/18