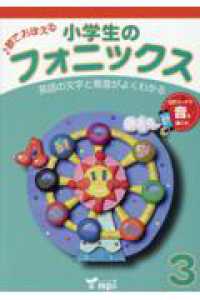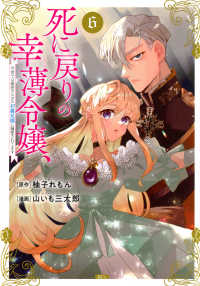- ホーム
- > 和書
- > 文芸
- > 海外文学
- > その他ヨーロッパ文学
内容説明
愛は成就されず、成就されるのは愛でないものばかり。十二月の最初の日曜日、十二歳になる侯爵のひとり娘シエルバ・マリアは、市場で、額に白い斑点のある灰色の犬に咬まれた。背丈よりも長い髪の野性の少女は、やがて狂乱する。狂犬病なのか、悪魔にとり憑かれたのか。抑圧された世界に蠢く人々の鬱屈した葛藤を、独特の豊饒なエピソードで描いた、十八世紀半ば、ラテンアメリカ植民地時代のカルタヘーナの物語。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ヴェネツィア
140
壮絶な小説だ。一貫して追求されされているのは愛なのだが、それはついに双方向性を持ちえなかったし、不可能性においてしか描くことができなかった。小説世界は18世紀半ばのラテンアメリカを舞台に展開するが、この地を植民支配していたのがアングロアメリカのようにプロテスタントであったなら、こうはならなかったのではないかと思う。しかも未だ異端審問の跳梁跋扈するスペインの、しかもブルゴスでありアビラなのだ。物語は世俗支配と宗教支配を否応なく受け入れざるを得なかった、この地に生きた人々の錯綜した情念を掘り起こしてゆく。2013/12/30
Gotoran
51
G.マルケス60歳代半ばで著した作品。12月の最初の日曜日、12歳になる侯爵のひとり娘シコルバ、マリアは、市場で額に白い斑点のある灰色の犬に咬まれた。・・・悪魔憑きとされた美貌の少女を祓うため遣わされた修道士だったが、その娘と恋に落ち激しく愛し合うも、信仰の不条理がふたりを引き裂いてしまう。ラテンアメリカの植民地時代(16世紀前半~19世紀初頭)を舞台に、絶大な力を持つ教会による抑圧、中世的な迷信の抑圧、人種的な抑圧、辺境の意識による抑圧を、この作品の中に垣間見ることが出来た。2019/12/07
松風
29
現実地続きの神話。魔術と信仰と知と愛が一度きに語られる辺境。いや、それどころか、辺境と中央も同時に語られている。ー「あなたがたの宗教は死の宗教だ。信仰が、死と向かいあう勇気と至福とを吹きこんでくれることになっている」と彼は言った。「私は違うー私は生きていることが唯一根本的なことなのだと信じている。」アブレヌンシオの所でカエターノが失った本にめぐり合うところが一番好き。2014/07/24
三柴ゆよし
21
救いがたい頽廃がはびこり、教会による抑圧が横溢する18世紀のコロンビアを舞台に、黒人奴隷の楽園に君臨し、アフリカの呪術の加護を受けた悪魔憑きの美少女と書痴の修道士が繰り広げる、土俗パワー全開の恋愛劇。読んでいるうちにうずうずして来て、これぞラテンアメリカ! と叫び出したくなった。『百年の孤独』で一時代を築き上げたマルケスの原点回帰であると同時に、その心憎いタイトルがあらわすとおり、愛という名の悪霊の、そのどうしようもなさについての洞察が随所に散りばめられている。ミニマムでありながら破滅的な傑作。2012/01/19
pico
19
打ちのめされた。臭い汚い暑苦しい…夥しい数の血塗られた狂乱に息ができなくなる。愛は悪霊なのだろうか。たとえ反吐を吐かれたとしても、こんなにも純粋無垢で生に対して正直な悪霊ならば、愛してやまない。「私は生きていることが唯一根本的なことなのだと信じている」抑圧から生まれた激しく美しい愛の物語に心酔する。2009/08/04