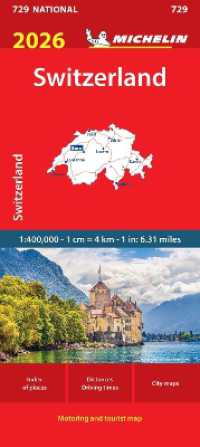- ホーム
- > 和書
- > 人文
- > 哲学・思想
- > 構造主義・ポスト構造主義
出版社内容情報
近代になって登場した「人間」は、いずれ終焉を迎えるだろう――。20世紀の文化人に大きな衝撃をもたらした、今なお革命的思想書。
内容説明
17世紀のベラスケスの名画「侍女たち」は、「人間」の不在を表現している。「人間」は、じつは近代になってから登場したものであり、それは時代に規定される知の枠組みである“エピステーメー”の歴史的変容によって、いずれ終焉を迎えるだろう―。古典主義時代の博物学、富の分析、一般文法の三領域が、近代の生物学、経済学、文献学へと変遷し、そこから人間諸科学が誕生するにいたる過程を、豊富な実証と精密な論理で説き明かす。20世紀の西欧思想界を大きく揺るがし、いまなお人々を魅了する革命的思想書。
目次
第1部(侍女たち;世界という散文;表象すること;語ること;分類すること;交換すること)
第2部(表象の限界;労働、生命、言語;人間とその分身;人文諸科学)