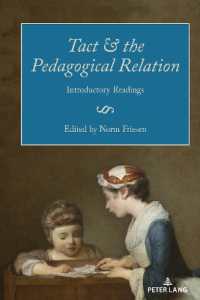- ホーム
- > 和書
- > 人文
- > 哲学・思想
- > 構造主義・ポスト構造主義
内容説明
愛欲の営み、性の快楽から、結婚生活の重視、倫理的規範の強化と増大へ…古代ギリシャからキリスト教社会への変容を辿る。
目次
第1章 自分の快楽を夢に見ること(アルテミドロスの方法;夢幻の行為)
第2章 自己の陶冶
第3章 自己と他者(結婚の役割;政治の働き)
第4章 身体(ガレノス;快楽の営みの養生法)
第5章 女性(夫婦の絆;独占の問題;結婚の快楽)
第6章 若者たち(プルタルコス;擬ルキアノス;新しいエロス論)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
優希
86
社会と性の関係を軸に語られるエロス。性行為の実践について述べられていきます。危険で抑制できない代償が伴うにも関わらず、人は何故性へと向かうのかというのが大きな問題提起として軸に据えられているようでした。愛が精神的価値であるためには社会の対応はどのようであったかを快楽の活用から節制へと変容した歴史はかなり興味深かったです。性そのものを自己的快楽へと向けることで、性が関わる社会構造が明るみになりました。ローマの性倫理からですが、ジェンダー論やフェミニズムを崩して性を述べる意味の重要性は大きかったでしょう。2016/01/28
きいち
34
何というか、極北。◇論旨ははっきりしてるし訳文も明解、でも、なんでフーコーがローマの性倫理にこだわってるのかが、自分には結局想像つかない。だって、我々が性を考えるのに、春秋の注釈や中観・唯識の戒律を手繰っていくような(あら、時代もぴったり)もんでしょう?確かにキリスト教の束縛からも現代の個人化からも離れられるし、俗流ジェンダー論やフェミニズムの図式化は崩せるけれど、いくらなんでも最晩年のフーコーが8年考えてそれで済むはずはないやろし・・。◇いったん棚上げだ、時代を戻して、筑摩や河出のコレクションに行こう。2016/01/12
roughfractus02
7
考古学的手法による言説分析から系譜学的手法による権力分析へ向かう最晩年の本書は、生政治を他者による自己の管理から自己の自己への配慮へ転回させる。前者が他者の管理の内面化なら、後者は自己をこの内面機構に閉塞させないための身体的作法である。著者はこの内面的機構が反省的自我を作り出して身体の力を削ぐと捉えると同時に、権力を権威的他者の行使する力ではなく、自己を修正しコントロールする力へとその概念内容も変える。その中で本書はヘレニズム期からキリスト教の時代にかけての若者への愛の変容を途切れた系譜を辿るように描く。2024/11/30
iwasabi47
6
『肉の告白』予習の為に再読。副読本として佐藤健一『禁欲のヨーロッパ』も先に読む。時代や目的の制約で女性関連の記述は弱い。家政への国家介入(相続・嫡出子や女性の限定的な財産権)や建前の自由婚(女性の初婚年齢12歳、男性との年齢差10歳以上)を押さえた上で読むといいかな。この辺は歴史学やローマ法とか勉強の課題。佐藤本に出てくる性欲より食欲節制が問題かも?とフーコーが少し言及していた。後代基督教的禁欲とヘレニズム的禁欲との微妙な差異を知るのが私の課題か。2021/05/11
Z
5
動を通して哲学を追放すること。他方でフーコーが告発してきた生権力に抗うこと。生権力とはマクロな人口という集団を対象にした管理統治のしくみであり、経済:社会学が補完し国家と社会の質的相違を見失わせる。性に着目すること。性とはあくまで個人が抱えるものであり、ギリシア人は日本でいうと剣道や柔道といった意味で、「道」として自己の性を管理する技術を思考してきた。養性術、恋愛術、家庭管理術等。ここでフーコーが強調するのはキリスト教のように万人に値するような性の規範をギリシア人は作らなかったこと。未完なのは惜しまれるが2016/04/02