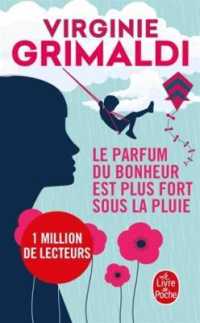- ホーム
- > 和書
- > 人文
- > 哲学・思想
- > 構造主義・ポスト構造主義
内容説明
一つの社会は権力、快楽、知の関係をいかに構成し、成立させているか。フーコー考古学の鮮やかな達成。
目次
第1章 我らヴィクトリア朝の人間
第2章 抑圧の仮説(言説の煽動;倒錯の確立)
第3章 性の科学
第4章 性的欲望の装置(目的;方法;領域;時代区分)
第5章 死に対する権利と生に対する権力
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
優希
81
性に対する研究でありながら、性の歴史を通じて権力への転換を叙述されています。権力、快楽、知の関係の構成を社会・医学・宗教から考察することで、性の解放と抑圧を体系的に考える試みが感じられました。性に関する権力をたどり、女性軽視に通じる生権力を批判する。そこに至る性のプログラムとしての歴史も語られています。性について語ることはスキャンダラスと言われがちですが、性の歴史でありながらも倫理や生き方を説いている名著だと思いました。現代にも通じる権力の見方を示唆し、問題提起をしているのではないでしょうか。2016/01/28
ケイ
73
良書。権力に対する抵抗について知りたかったのが読んだ動機。作者が説く「性」についての談義が、今のLGBTQにつながってきていると感じる。2025年の今ではAIDSやコロナなどの感染病への懸念を視線として持ってしまうので、性の快楽や解放の危険さを書かれている通りに納得するわけにはいかない。それでも、いや、だからこそ、書かれた頃よりずっと前の、性に対しての告解、告白の意味を理解できる。女性の苦痛(出産や性被害者として)が力と性に関する問題を語る上で飛ばされている。さらに読み込みたい。2025/09/21
ころこ
37
ヴィクトリア朝(19世紀)には抑圧された性というイメージをつくったフロイトがいて、他方で労働力の体力管理と労働力の再生産という相反する目的のためのセックスの権力に対抗するマルクスがいる。両者をつなぐと、自由な性と労働力を管理する性は容易に両立できないため、抑圧された性のイメージが必要となるとなります。しかし、著者はこうはいっていないのがややこしいところです。本書は読み易い訳文ですが、迂遠な断片的具体例が多く、文意をつかみ辛くしています。例えば学校の性教育は生徒が殊更話題にしないのに、あるとき教師が突然語る2021/01/23
燃えつきた棒
34
残念ながらピンと来なかった。もちろん、残念なのは僕の理解力の方だろうが。 読めども読めども近づけぬこと、カフカの「城」のごとし。2021/02/04
きいち
33
文章が難しいわけではない、性への抑圧の少ない近世&現代と、妙に禁欲的だった近代、共に経験してきた日本人にとって、特にとても理解しやすい文脈だと思う。◇なのだけれど、でも、幾度か読み返してみてもさっぱり読めてる感覚にならない。多くの力のせめぎあいそのものである権力を考えていくにあたって、現在のそれは人々の「生」が舞台、だから最適なテーマとしてフーコーが選んだのが性・・などと物語化した瞬間、フーコーが論じようとしている「生-権力」からかけ離れていくような気がするのだ。◇…うん、いったん置いて、2巻いこ、2巻。2015/10/05
-
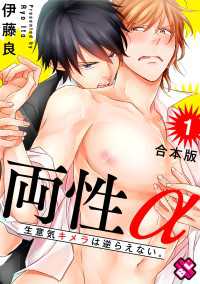
- 電子書籍
- 両性α 合本版1~生意気キメラは逆らえ…
-
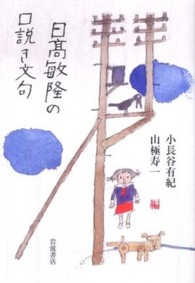
- 和書
- 日高敏隆の口説き文句