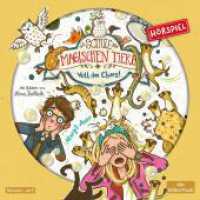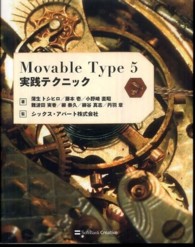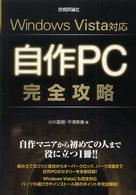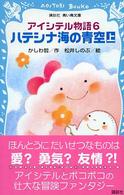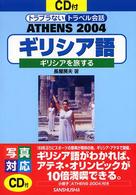内容説明
国際的美術家による芸術と文明を巡る12章。
目次
神が仏になる時
時間よ止まれ
本歌取り
狐眼の女
引かれ者の小唄
あるべきようわ
射干玉の闇
垂乳根の母
利休・モダン
鬼畜の言説
永久戦犯
追記
連載を終えて
著者等紹介
杉本博司[スギモトヒロシ]
1948年東京生まれ。立教大学経済学部を卒業後、ロサンジェルスのアートセンター・カレッジ・オブ・デザインで写真を学ぶ。74年よりニューヨーク在住。現代美術作家として活動するかたわら、古美術商を営んでいた時期も(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
かりさ
64
溢れるばかりの豊かな知識を言葉にのせ、紡がれる文章は、私の思考も刺激を受け、知識への渇望が満たされてゆく。読むごとに杉本さんの絵画や芸術、古美術や考古学にまで関する知識の豊富さ、多岐に渡る興味の対象にただただ驚きと感嘆を得、その文体の流れに漂う心地よさを感じました。冒頭文からもう鷲掴みにされます。巧みに織り成される杉本さんの言葉に惹かれ博学の世界へ導かれていきます。中でも「時間よ止まれ」は印象深く、ここからまた新たな興味と知識を得てゆく感覚がたまらなく良い。『現な像』…タイトルまで美しく素晴らしい。2017/09/17
どんぐり
61
「うつつ」な像と読む、古美術商で現代美術作家の芸術と文明を巡るエッセイ12章。杉本の代表作《海景》《ジオラマ》《劇場》シリーズを一堂に会して見たのは2年前、千葉市美術館で「趣味と芸術-味占郷」と題した展覧会だった。本書の「神が仏になる時」には、この展覧会場にあった平安時代の「十一面観音立像」が、「仏は常に在ませども 現ならぬぞあはれなる 人の音せぬ暁に 仄かに夢に見えたまう」の今様の歌とともに紹介されている。この本には杉本の美術蒐集品と制作作品の写真を見ながら読む楽しさがある。2018/05/13
zirou1984
35
前作『苔のむすまで』に続くエッセイ集。ゴッホと禅僧についての類似性や、戦争期における米国ジャーナリズムでの日本人ついての言及といった刺激的な考察が多く、中でも歴史と写真の起源について言及しながら著者の特異な時間感覚が垣間見られる「時間よ止まれ」は抜群に面白い。また、写真論や映画論で近いものを感じていたスーザン・ソンタグが亡くなった後、その映画の仕事を引き継いでいたというのは驚きだった。読み進めるごとに杉本博司というのは写真家ではなく、永劫の時間を封じ込めようとする芸術家なのだという感覚が強くなっていく。2016/10/15
アマヤドリ
10
杉本さんの文楽が楽しみ。2011/07/26
のんたんの
6
『自我の発露として作品を造りえるのではない、私の自我は、長い民族の歴史の果てにたどり着いたこの地で見失ってしまった遠い先祖の地を垣間見るための、盲人の白い杖にすぎない。私はただこつこつと過去への道をたたき、帰ってくる響きをたよりに、導かれるがままに作品を作る。」タイトルそのまんまの方だと思った。2009/11/21