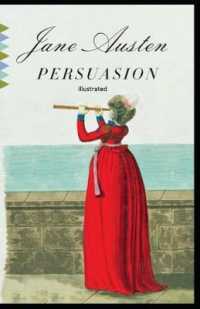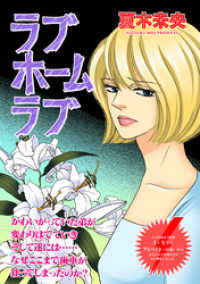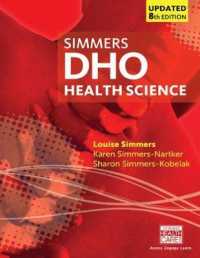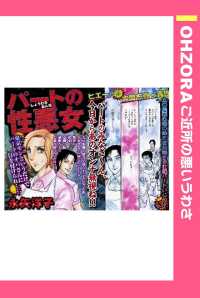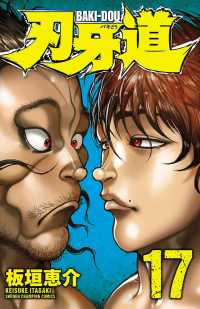内容説明
桜の花の咲く頃に出会うはずのない二人が接近した…。凄惨な時代に翻弄された十一歳の少年。歪みを知らない信念が守り通そうとしたものは何だったのか。極限状況の“沖縄”を研ぎ澄まされた筆致で描く、話題の長編小説。
著者等紹介
古処誠二[コドコロセイジ]
1970年福岡県生まれ
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
クリママ
43
今まで読んできた沖縄戦の様相とはずいぶん違うものの、その時の沖縄の人たちの暮らしがどのようなものであったのかを知る。沖縄口は禁じられ、すべて標準語である。簡潔で穏やかな語り口は最後まで貫かれているが、後半に行くに従い動悸が早くなる。友達と泣き笑いバカを言い、そして信頼できる大人に見守られて育つはずの11歳の少年が、真摯な気持ちで労を惜しむことなく皇軍のために働き、大人になることを急かされる。聡明な少年はわかっていた。でも認めたくなかった。動悸は収まらない。2016/11/23
色々甚平
13
[直木賞候補]沖縄戦まっただ中、皇軍に好意的な少年が、戦争を生き抜いて行く中での葛藤が描かれる。少年の心の葛藤までもが標準語になっていたのは方言撲滅運動の中育ち、方言を使わなくなった世代に突入したということなのだろうか。少々文章が読みにくいように感じたが、日系アメリカ人がスパイとして入り込むミステリー要素もさながら、威勢よかった兵たちは一部山賊まがいになった時の住民たちの失望感と絶望感が印象深い。2015/11/14
HoneyBear
11
短いがずしりとこたえた。少年の体験を中心に物語は小さくまとまっているが、そこで語られる沖縄戦の様相と死地での人間同士のやりとりは深く重い。日系米兵が見た日本兵の戦いぶりは「勝敗は度外視されていた。度胸と積極性を示す戦いに敗れた彼らは、その後を絶望的な戦いで染める。心の支えは死後の評価だった」と。救いのない状況下に「標準的な日本語を身体に馴染ませる努力をした者同士」の心の交錯の美しさと残酷さを鋭く描ききっており、心を抉られるような読後感が残った。『七月七日』に続いて素晴らしい小説だった。2014/08/13
つる
2
これが確か初古処。ルールに行って古処の虜に。
ミツオキンギョ
2
接近とは、相手がだったのか、それとも自分がだったのか?誰もが苦しんでいるからこそ助けたいという純粋な気持ちから人に近づく。お互いの心の距離に接近しすぎて気が付いた現実。生と死との接近。考えてもいなかった恐ろしい時代の一面を知った。 2012/12/24