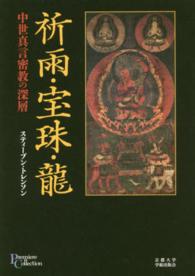内容説明
“建築”が表象するのは国家の欲望なのか?旧時代を打破する革命の予兆なのか?西欧モダニズムを独自の形で変形し受容した日本近代建築の変遷を大胆に再構成し、自らの活動を見つめ直す表題作ほか、イセ、重源、カツラからインターネット時代の新都市像まで、世界的建築家による日本=建築論の記念碑的集成。
目次
第1章 建築における「日本的なもの」(「趣味」と「構成」;「構築」と「空間」 ほか)
第2章 カツラ―その両義的な空間(近代主義による読解(ブルーノ・タウト;堀口捨己;丹下健三)
雁行‐配置 ほか)
第3章 重源という問題構制(純粋幾何学形態;天笠様 ほか)
第4章 イセ―始源のもどき(イセという問題構制;持続のなかのアイデンティティ ほか)
著者等紹介
磯崎新[イソザキアラタ]
1931年生まれ。東京大学数物系大学院建築学博士課程修了。1963年磯崎新アトリエを設立、以来、国際的建築家として活躍。建築作品として、大分県立図書館、群馬県立近代美術館、つくばセンタービル、ロサンゼルス現代美術館(MOCA)、水戸芸術館、バルセロナ市オリンピック・スポーツホール、秋吉台国際芸術村、なら100年会館(奈良)など多数
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
- 評価
孤独な建築家の本棚
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ひろし
45
日本的な建築とは何か、この問いに関して作者は3つの建築に着目する。外国人の権威により現代的な価値を見いだされ再評価された桂離宮。変革期に新技術を導入したが普及せず、プロデューサー重源とともに消え去った大仏様(東大寺南大門)。天皇の正統性を表すために飛鳥時代に作られた伊勢神宮の形態と式年遷宮という儀式。桂離宮では建築の解釈、大仏様では様式の受け入れられ方、伊勢神宮では発生の経緯という、建築物そのものの特徴でなくそれぞれの建築の捉え方から日本的建築とはの意味を考えている。2018/08/16
zirou1984
22
一読ではその思考を追いきれなかったが、再読することでその問いが持つ射程の広さを堪能することが出来た。まとめるなら「日本的なもの」という問いは外部との接触からしか産まれえず、時代によってその解釈は変わり続け、その起源自体は隠されているということだろう。桂離宮、東大寺南大門、伊勢神宮について読み解こうとする磯崎新のテクストは、問いの立て方によって思考という空間を創りだす。そして時間と空間を繋ぐ<間>に何かを読み取ろうとする心性―それは忖度でもある―そのものにこそ、自分は「日本的なもの」を読み取ってしまうのだ。2018/06/06
ネムル
14
「日本的なもの」への問いかけには外部からの視線にさらされることで、解釈され続ける。このあたり帝冠論争にも非常にわかりやすいが、同時にまた磯崎が内乱という補助線を引いてくるのが興味深く、日本建築というイメージから一番遠い東大寺の項目を興味深く読んだ。しかしまあ、初学者向けの本でないのはわかるが、図版も少なく、すごく不親切だ。石元泰博の写真や『ルネサンス 経験の条件』などをぱらついたが、やはり難解。2018/06/09
tyfk
5
「『古事記』を再語りすることによって本居宣長が『古事記伝』を著したことをあらためて再語りする小林秀雄の『本居宣長』は、七世紀末にはじまった伊勢神宮の式年造替の制度が、その初源のやりかたを徹底して〈もどく〉という"擬態"を反復することで、かたちを不変に固定し、永続性を高めるユニークな手段となっているのと同様のやりかただとみえる。」p.1232024/05/02
c3po2006
1
★★★★★2024/10/29
-
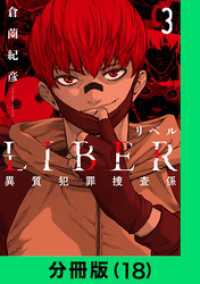
- 電子書籍
- LIBER-リベル-異質犯罪捜査係【分…




![Cool Down - Malbuch für Erwachsene: Aachen [Plus Farbvorlage] (2016. 68 S. 3 Farbabb. 279 mm)](../images/goods/ar/work/imgdatak/39468/3946825591.jpg)