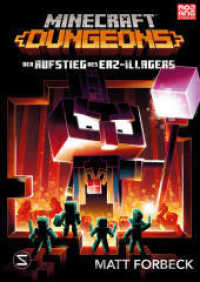内容説明
動物行動学の第一人者が生きものたちの知られざる営みを分かりやすく語ります。もちろん人間についても。
目次
町の音
琵琶湖の風
ギフチョウ・カタクリ・カンアオイ
犬上川
ショウジョウバエの季節
八月の黒いアゲハたち
セミの声聞きくらべ
秋のチョウ
真冬のツチハンミョウ
冬の草たち〔ほか〕
著者等紹介
日高敏隆[ヒダカトシタカ]
1930年、東京生まれ。東京大学理学部動物学科卒業。東京農工大学、京都大学教授、滋賀県立大学学長を経て、現在は総合地球環境学研究所所長。2001年、「波」連載の「猫の目草」をまとめた『春の数えかた』(新潮社)により、エッセイスト・クラブ賞を受賞
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ceskepivo
12
読みやすい。普段は何気に見過ごしている動物、昆虫、植物の生態を専門家の見地から分かりやすく解説している。狸のオスは立派だ。メスの出産に立ち会うだけでなく、メスの出産中に背中をなめてあげたりする。でも、出産後に餌あさりに行ったメスは、子供を守っているオスには餌を運んでここない(涙)。ギリシャのアリストテレス曰く「セミの夫たちは幸せである。なぜなら彼らの妻たちはしゃべらないからである。」??2014/08/13
greenman
7
人間はどこまで動物かと考えた人は多いと思う。というより人間は動物の1種でその中で頂点を占めているか、あるいは動物からすでに離れていると考えるか、それとも本能と理性がぶつかり合う特別な存在か・・・など様々な議論がある。本書はエッセイで構成され、人間とはどういう存在かということを直接語ることは少ないけれど、昆虫や蝶々に木々など普段見かけるのにただの虫とか木としか考えられなくなっている現代人にどれだけ生活の中で生態系を見落としていることに気づかせてくれたり、人間自身もその中に入っていることを気づかせてくれる。2012/10/24
isuzu
4
前作の『春の数えかた』が気に入ったので、続き。相変わらず読みやすくて楽しい。生きる、ということ(道徳的な意味合いのそれではなく)について、しんしんと考える。戦わないと死ぬのは時代のせいでも人間だけに特有のことでもないんだよなぁ。2012/01/26
okaka
3
どちらかというと文芸寄りのエッセイでさらさら読める。生き物の世界はすべてが網の目の様につながっているので一点だけ見ちゃダメと言うのが著者の一貫した主張でありましょうか。2014/04/15
ふうか
2
日高さんの考え方がとても好き。教育を学ぶ私にとっては、考えるよい機会を与えてくれた本だった。特に大学について述べていたところには付箋を貼った。2018/02/23