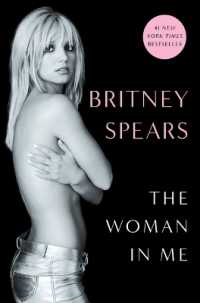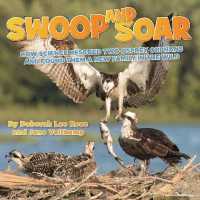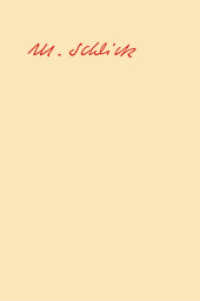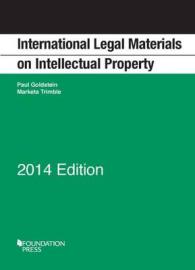出版社内容情報
春夏秋冬、さまざまな行事を大切にする京都の茶商。伝統と知恵にあふれた茶の文化とふだんの暮らしを丁寧につづるエッセイ。
京都の老舗の茶商が伝える、大切にしたいささやかな暮らしの知恵。四季折々の行事とともにある暮らしを大切にする京都の人々。旬と名残り、お祭、茶花、贈りもの、毛筆の手紙、祝いごと、出会いと別れ――自然の恵みと人の知恵が織りなす茶の文化が、そのまま私たちの日常へと続いている。一服のおいしいお茶がもたらす豊かな時間とは。一保堂茶舖・六代目夫人がつづる歳時記。
内容説明
おいしいお茶を召しあがれ。京の老舗茶舗が受けつぎ伝える、大切にしたい暮らしの歳時記。
目次
京都寺町 春・夏・秋・冬(新茶のころ;冷たい玉露 ほか)
一保堂のこと(あきない;嘉木のこと ほか)
お茶まわりのおはなし(急須のこと;茶碗と茶托 ほか)
お茶の時間(おもち;火 ほか)
著者等紹介
渡辺都[ワタナベミヤコ]
1953年、島根県生まれ。フェリス女学院大学卒業。夫が六代目を継いだ「一保堂茶舗」で、お茶の愉しみを伝えるべく努めている(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
- 評価
京都と医療と人権の本棚
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
シナモン
166
京都一保堂茶舗の六代目夫人が綴るお茶にまつわるエッセイ。ここ一番って時にうまくいれられないっていうのは分かるなぁ。文章も読みやすくきっと優しくて朗らかな方なんだろうなぁと親しみがわきました。美味しいお茶のいれ方はもちろん、雁ヶ音、大福茶の由来とか、いろいろ勉強にもなりました。「裁縫の半返し縫いのように、行きつ戻りつしながら秋はゆっくりと進んでいきます」京都の四季を感じながら、ほっこり爽やかな読書時間を持てました。丁寧な暮らしってやっぱり心地よいな。2020/11/24
itoko♪
60
京都の老舗『一保堂茶舗』の女将さんによるお茶のエッセイ本。季節のうつろいに合わせたお茶の楽しみ方が、御自身の生い立ちやエピソードを交え、紹介されています。時折出てくる、京言葉に和みます。伝統あるお茶の世界を守りつつも、常に新しい仕掛けに挑む姿勢や取り組みが素敵な女性です。ただ、商品パッケージ写真やイラストがもう少しあれば、もっと魅力が伝わったかなぁという印象です。2015/10/18
HMax
33
老舗お茶屋の一保堂茶の六代目夫人が優しい調子で語るお茶にまつわるエッセイ。義母との思い出話しや雁ヶ音茶の名前の由来、心も体もほっこりとするエピソードがたっぷり。この本で教えてもらった煎茶の淹れ方、ちょっとした工夫でとても美味しくなりました。2020/12/06
Mayu
12
京都の一保堂さんの奥様の著作。古くからのお家を受け継いでいくことには大変なご苦労がおありだと思いますが、あまりそういうところを前面に出さず、ご実家の出雲との違いや、嫁いできて初めて知ったことなど、それぞれに興味を持って、様々な工夫を楽しんで来られたように書かれていて、とても素敵でした。お正月に頂く大福茶の由来や、北陸出身の実家の父が茎茶を好きな理由など、身近なところで発見があり、楽しく読めました。日本茶産業の方が、伝統を守りつつも、新しい時代にあった商品を考案されてきた努力にとても感銘を受けました。2015/08/18
和草(にこぐさ)
9
丁寧な語り口の文章が印象に残りました。手軽に飲めるペットボトルのお茶を飲むことが多かったのですが、茶葉のほどける時間を楽しみながらゆったりとお茶を飲むことの良さを教えてもらいました。2016/03/15