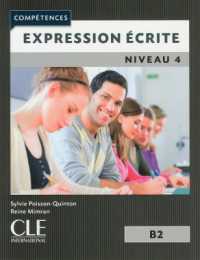出版社内容情報
開国まで隠れ続けたキリシタンの村。信じている、とつぶやくことさえできなかった人間たちの魂の叫びがここに甦る。慟哭の歴史巨編!
内容説明
初めてだった。これほどに、自分を認めてくれる教えは。だから、信じることに決めた。百姓たちは、苦しい日々を生き抜くためにキリシタンになった。なにかが変わるかもしれないという、かすかな希望。手作りのロザリオ。村を訪れた宣教師のミサ。ときの権力者たちも、祈ることを奨励した。時代が変わる感触がそのときは、確かにあった。しかし―。感涙の歴史巨編。戦国期から開国まで。無視されてきたキリシタン通史。
著者等紹介
帚木蓬生[ハハキギホウセイ]
1947年、福岡県生れ。東京大学仏文科卒業後、TBSに勤務。2年で退職し、九州大学医学部に学ぶ。現在は精神科医。1993年『三たびの海峡』で吉川英治文学新人賞、1995年『閉鎖病棟』で山本周五郎賞、1997年『逃亡』で柴田錬三郎賞、2010年『水神』で新田次郎文学賞、2011年『ソルハ』で小学館児童出版文化賞、2012年『蠅の帝国―軍医たちの黙示録』『蛍の航跡―軍医たちの黙示録』の二部作で日本医療小説大賞、2013年『日御子』で歴史時代作家クラブ賞作品賞をそれぞれ受賞する(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 3件/全3件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
いつでも母さん
115
受験の時は菅原の道真に、妊娠5ヶ月の戌の日には安産の、結婚式は神前で、クリスマスにはパーティを、身内が亡くなった時はお寺で・・なんとも自分の都合の良いように神社仏閣神様、仏様におすがりしてきた私。(時には神も仏もいないと嘆き・・)全てに神が宿るとも聞く。日本には八百万の神がいるとも・・天地創造の神・・あゝ、こんな私がこの作品を読んでも良いのでしょうか?信仰は心のなかにある・・はず。感想は下巻にて。2017/10/29
しいたけ
109
戦国の世、もっとも小さき者、百姓がキリストを信じた。目まぐるしく変わる情勢に、怯え、歓喜し、ひたすらに祈る農民たち。切り口が変われば呼び名も、史実でさえ変わる。西軍が破れるなかイエズス教徒の救出のため奔走し城を落としていくのは黒田シメオン如水。大村バルトロメウ純忠や、有馬プロタジオ晴信、小西アグスチノ行長らが駆け巡る。とはいえ主人公は地方の農民である。「太閤が亡くなったらしい、徳川某とは一体どげな人か」。後世まで語られる歴史の片隅で信仰は試され磨かれていた。土嚢を積み上げるごとく固めていく信仰の尊さ。2018/04/03
のんき
88
潜伏キリシタンが世界遺産に、というニュース。偶然かなあ。隠れキリシタンのお話しでした。戦国時代、九州の小さな村で多くの人がキリスト教の信者になります。人を殺さない。一人の夫に、一人の妻。とかが良かったのかなあ。でも、やっぱり、慈愛、人が人を思いやる心が一番だったんだと思います。日本語もわからない外国人宣教師。何年もかかって日本に来て、ひろめるのは大変だったんだなと思いました。どうして禁止されながらも、命が危ないのに、そこまでやるんだろう。宣教師も信者もすごいな。当時のことがよくわかる作品でした2018/05/04
のぶ
77
まだ上巻を読む限りだが、とても真摯な視点で描かれた物語だ。16世紀後期に九州の久留米藩を中心に、大友宗麟からイエズスの王国を築くように指示を受ける。上巻の前半ではイエズス会の布教活動も順調で、多くの農民にキリスト教は広がっていく。やがて中盤を過ぎ禁教令が発せられた所から、物語に暗雲が立ち込めてくる。しかし布教活動は止まず、信仰も広がって行く。宣教が広がっていく背景に、生活の苦しさがある事が同時に描かれている。この先大きな波乱が待ち構えているように感じられたところで上巻は終わり。感想は下巻で。2018/05/19
それいゆ
62
1569年から1867年までのキリシタン通史でした。宣教、禁教、殉教、棄教、潜教、開教すべてを網羅した隠れキリシタンの秘史でした。上巻ではキリシタンたちの 信仰のようすの話が淡々と進み、たいくつな感もありますが、下巻では激動の展開となり弾圧の歴史が語られるのでしょう!アルメイダ、オルガンチノ、コエリョ、ロヨラ、小西行長、高山右近、ヴァリアーノ、ペトロ岐部、中浦ジュリアンなど聞いたことのある名前が次々と登場して、「日本キリスト教史」という教科書を読んでいるようです。2017/10/17
-
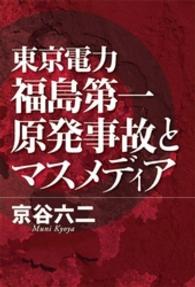
- 電子書籍
- 東京電力福島第一原発事故とマスメディア