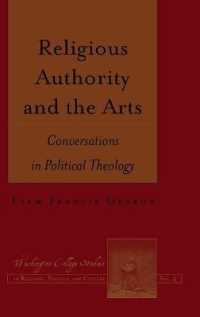内容説明
希望と絶望、理性と感情、運命、哀歓…。必死に生き抜いてきた患者さんが教えてくれたことは、千年に一度の大震災の後も変わらぬ心理が内包されていた。
目次
第1章 希望という名の絶望(死ぬまで頑張れ!?;希望という名の絶望;人を殺す理由、あるいは死なせる基準)
第2章 タダが人間を堕落させる(偽善の「説明責任」;「冷静な対応」ってなんだ;聖人君子が国を滅ぼす;「議論を尽くす」はどこまでか;未熟と老耄;情報メタボ;「すばらしい世界」のガス抜き;タダが人間を堕落させる;そんなに悪いか、バクチ打ち)
第3章 人生はなんのため?(試験勉強なんのため?;本当に「教養」は役に立つのか;天国と地獄の「線引き」;留学しない若者たち;なんのために学ぶか;仕事はなんのためか)
著者等紹介
里見清一[サトミセイイチ]
本名・國頭英夫(くにとう・ひでお)。三井記念病院呼吸器内科科長。昭和36年鳥取県米子市生まれ。昭和61年東京大学医学部卒業。東京大学第四内科、東京都立墨東病院救命救急センター、横浜市立市民病院呼吸器科、国立がんセンター中央病院内科などを経て平成21年3月より現職。日本癌学会・日本臨床腫瘍学会・日本肺癌学会評議員、厚生労働省薬事・食品衛生審議会医薬品等安全対策部会委員、杏林大学客員教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
nchiba
4
人の生死というものが単純なものではないことを改めて知った。現実を無視した観念的な議論はまず役に立たない。死を見つめてきた臨床医でならではの説得力があって面白かった。死を見つめることは生きることを考えることでもある。学ぶこと、働くことの意味についても考えさせられた。二十台前半の若い人たちに是非読んでもらいたいと思ったな。2011/10/10
もけうに
3
里見先生の著作は数多読んできたが、本書が一番良かった。医療の経験を通して見た、社会及び哲学。基礎科学・形而上学の必要性、何故人は仕事をするか、等私も昔から考えてきたことが多い。新型インフルに係る件は、コロナ禍を予期しているようだ。医療ドラマが常に人気なのは、誰もが根本的に「人の生死」「人間の死に様」に関心があるからだと思う。2022/04/06
讃壽鐵朗
1
この本のような社会全般に渡って言いたいことを言ってのけているのを読むのは、小心者に取っては実に気分のいいものだ。 本当に、こんなこと、こんな表現までしていいのかと怖くなるほどの箇所が多々あり、まさにそれを読み進むのは、未知の細くて暗い道を歩いているような感じになってくる。とても一々その箇所を書き連ねるわけにはいかないほど沢山ある。 2013/11/13
Dr G-san
1
学会名物國頭先生。読んで良かったです。2012/01/14
いのお
1
がん臨床医のエッセイ。世間話的なところはいかにも新潮45の読者層に合った保守オヤジの雑談だが、医療について、生について、死についての話は溜め息しか出てこないくらい深すぎる。特に治る見込みのない末期がん患者に対して最大の希望は治療法という選択肢を与えることだが、それは「助けられる人を効率的に助ける」という医療の現場とは反対に進む行為であり、そのジレンマにはかける言葉が見つからない。医者の本分は「患者を(あの世に)送ること」という話には何十年苦しんできた著者の最大級の誠意が感じられた。第一章と最終章はいろんな2011/09/13