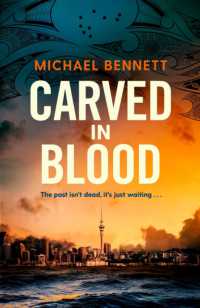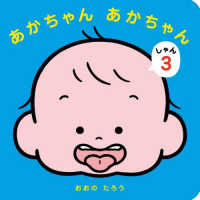内容説明
5歳児ぐらいの身長、一度聞いたら忘れられないへんな声、ずば抜けた頭脳を持つぼくの親友オウエンを、ある日過酷な運命が襲った。ピンチヒッターで打ったボールが、大好きだったぼくの母の命を奪ったのだ。ぼくは神様の道具なんだと言い続ける彼にとって、出来事にはすべて意味がある。他人と少し違う姿に生れたオウエンに与えられた使命とは?米文学巨匠による現代の福音書。
著者等紹介
アーヴィング,ジョン[アーヴィング,ジョン][Irving,John]
1942年アメリカ、ニューハンプシャー州生れ。ニューハンプシャー大学を卒業後、レスリングのためにピッツバーグ大学に通学、その後ウィーン大学に留学、ヨーロッパをオートバイで放浪する。帰国後アイオワ大学創作科でヴォネガットの指導を受けた。後にはレイモンド・カーヴァーとともに後進の指導にあたる。’68年『熊を放つ』でデビュー、’78年『ガープの世界』を発表し世界的なベストセラーとなった。現代アメリカ文学の旗手と称される
中野圭二[ナカノケイジ]
1931年山口県生れ。慶應大学卒。慶大名誉教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ヴェネツィア
389
J・アーヴィングは初読。1989年の刊行なので、ほぼ最先端のアメリカ文学。上巻を終わった段階では、難解さに困惑といったところ。訳文から推察するに、原文で用いられている言葉も平易だと思われる。文体表現も特に変わったところはなさそうだ。まず、時間の構成が特異である。上巻では基本的には「ぼく」(ジョン)とオウエンの1952年から1958年(ぼくたちは10歳から16歳)が語られるのだが、そもそもそれは1987年時のトロントでの回想であり、しばしば時は87年に戻る。しかも、少年時のエピソードも単線的な時間において⇒2021/01/21
ケイ
121
5歳児くらいの身長しかないオウエン。みんなにバスケットボールみたいに抱っこリレーされても怒らない(可愛がっているのだから)。ネズミみたいな声だって、神様の考えだと思っている。頭もよく、親友もいて、普通に子供として過ごしている。彼がとことん違うのは、彼の不幸や彼がもらたらす不幸が、神が彼の手を借りてしていると信じていること。ジョンの義父ダンは偏見なく物を見る人で、彼はオウエンの考え方をその家庭環境のせいだと思う。ダンだってジョンだってオウエンを愛しているから彼を恨まない。でも私なら彼を許せないと思う。2016/07/16
扉のこちら側
81
2016年229冊め。【156-1/G1000】11歳でも5歳児程度の体格しかない小人症で、そういう風に生まれついたのは神様から使命を与えられているからだと心の底から信じているオウエンと、出生の秘密を抱えるジョンの友情譚。日本でいう『不思議系』キャラのオウエンは、わき目もふらずに生き急いでいる印象。並外れた知性を感じるが、下巻ではどうなっていくか。2016/03/31
Vakira
52
文庫本の表紙絵には動物の絵。アーヴィングさんの物語は動物たちが案外重要な役割を果たすことがある。アーヴィングさんと言ったら熊のイメージでしたが今回はなんと!珍獣アルマジロ。もう、表紙からワクワクが止まらない。ん?「ブリキの太鼓」のオスカル?僕の親友オウエンは11歳にして背の高さは5歳児ほど。しかし、オウエンはオスカルと違い、自分のコントロールで成長を止めたわけではないようだ。11歳にして聖書を読破し、哲学的発言をする背の低い僕の親友オウエン。多分オウエンは僕の母さんが好きだ。僕以上に・・・・2025/08/28
Ryuko
28
5歳児の身長、奇妙な声を持つオウエン。彼の打ったボールが主人公の母を死なせることになる。物語はぼくの子供時代(1950年代)と大人になってから(1987年)を織り交ぜてすすむ。大学に入ったふたり、これからどうっていくのか。下巻へ。アーヴィングの作品は、これまで「ひとりの体で」しか読んだことがないが、同じような構成、同じような主人公の境遇だ。アーヴィングの定番なのかな??2018/01/10