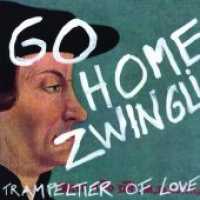1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ヴェネツィア
435
下巻に入っても鯨の蘊蓄はとどまることなく、モビー・ディックとの格闘は最後のわずか3章のみであった。本書は、かくのごとく構成からしても破天荒な作品である。構成の全体を俯瞰するならば、語り手のイシュメールはあるいはドン・キホーテに擬えられるかも知れない。エイハブはその幻想の中で、さらに純化されたドン・キホーテといった二重構造を持つことになる。そして、彼が希う存在である白鯨が神のごときもの(白いというスティグマを明確に背負っている)であるとすれば、エイハブは求めつつ報われることがない人間の象徴であるのだろうか。2022/06/17
lily
147
『トリストラム・シャンディ』や『ユリシーズ』と並ぶ形式に囚われない文学の自由の高さ。それに加えて燃える熱量と狂気。読者をも漂流させる引力。悲しみより喜びが多いような人間は真実の人間ではありえない、人間もどきであるか、まだ人間になりきっていないか。書物についても同じだ。2019/08/30
takaC
69
132章の最後にエイハブが慄っとした時には自分も慄っとした。スターバックスコーヒーの店名は、Pequod(ピークォド号)にするかStarbuck(スターバック航海士)にするかで迷ったといわれているくらいなのだから、アメリカ人は相当モビーディックが好きなんだろうな。2015/02/21
アナーキー靴下
60
イシュメールは元々鯨知識豊富な人間だと思って読んでいたけれど、この凄絶な体験を経て鯨に偏執的な興味を持ったと考えたほうが自然かも、と気付いた。一人生き残った者が、その体験を表現するために、他人に伝えるために、理由を知るために、意味を見出だすために、世界中の鯨に纏わる文献を読み漁り、このイシュメールがあるのだと。彼の知識と感覚は一般人から乖離し、伝わらないことに気付かない。上巻の訳者ノートに、発売当時読者に受け入れられなかったとあるが、それ自体がまさにいい例だ。誰も彼ほど彼の体験を想像できない。やるせない。2021/02/09
みくろ
54
下巻においても鯨学が止まらない。鯨の身体のしくみや捕鯨の道具についてなど詳細に書かれている。鯨に興味がない方にとっては退屈かもしれないが、上巻でもう虜にされていた私にはとても面白く。ただエイハブと白鯨との闘いはちょっとあっけなかった気がします。それだけモービィ・ディックが強かったという事か…。個人的に印象に残ったのはやはりピップか。強いが上に狂ったエイハブと弱いが故に狂ったピップの不思議な繋がりが切ない。しかしやはり捕鯨シーンは物語として読んでも残酷に感じますね、日本にとっても関係のある問題、難しい…。2016/02/24
-

- 洋書
- QIMMIK
-

- 電子書籍
- あなたの後悔なんて知りません【タテヨミ…