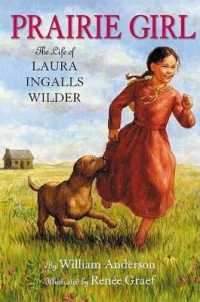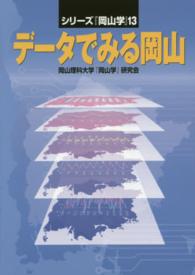内容説明
少子化が進み、塾やスポーツクラブ、フリースクールが認知された今、学校は役割を終えたとも言われます。では学校に何が求められているのか?この問題に応えようと、若い記者たちが懸命に取材しました。生徒の悩み、親の不満、教師の苦労を互いにぶつけ合った、本音満載のレポートです。改革に取り組む意欲的な例も多数紹介。地域に愛される学校にするためのヒントが見つかります。
目次
第1部 学校を見捨てる子供と親たち(不登校―「学校に行かなければならない理由」がない;山村留学―温かい居場所が学校にはなかった ほか)
第2部 苦悩する教師たち(教育困難校―「毎日が自分との格闘だった」と語る女性教師;自問自答―生徒を「育てる」ことに、やり甲斐を見出す教師 ほか)
第3部 学校再生への新しい試み(子供の居場所―大震災後の過酷な環境の中で見えた理想の教育;地域の拠点―震災で消えた“学校の垣根”を再びつくらないために ほか)
第4部 魅力ある学校づくりへの提言(自由選択―現場に必要なのは市場原理を導入すること;スリム化―学校自ら不必要な役割を放棄すべき時代に ほか)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
有智 麻耶
0
広いテーマを具体的な話をもとにしながら簡潔にまとめていて、非常に読みやすかった。最後に出した回答も、理想として掲げるにはいいのではないか。実現できるならするべき内容なのだから、理想論だと一蹴するのはあまりにも無責任。でも実際、家庭も学校も地域社会も疲れ切っている現状でどうすればいいのか。明確な答えが出ない問題ではあるが、国をあげて考えていかなければならないだろうね。2014/02/01
朝長耕平
0
ブックオフで見つけた本。これに答えられなければプロではないが・・・。 いや、勉強になりました。2013/08/27
うたまる
0
「だって、どんなに先生を信頼していても、いじめの問題は友達にしか相談できない。生徒の複雑な上下関係なんて、先生には分からないでしょ……。それに先生には悪いけど、中学生にもなったら、心の中までのぞいてほしくない」2011/08/10
Mikio Akagi
0
全体的に暗い事例が多い。不登校、学級崩壊、特に先生の苦労の話を強調したトーンになっている。そういった生徒や先生ばかりでは無いだろうとも思う。 この本から学べた事は、 ・授業を表明的に上手に教えることより、人間力のある師として生活指導を効果的に行えるコミュニケーション能力が先生には求められる。 ・行き過ぎた個性尊重は放任 ・行き過ぎた集団管理は孤独 ・生徒一人一人が気にかけてもらっているという安心感を感じることが大事 ・居場所(帰属意識)を持ち、役立っているという実感(承認)を得ることが貢献意識を育てる2019/10/24
-
- 洋書
- Prairie Girl