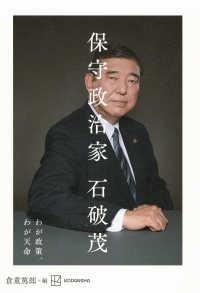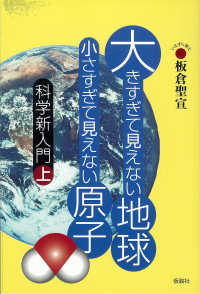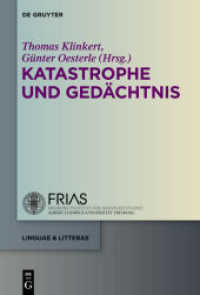内容説明
日本外交にとって戦後最大の未解決問題である北方領土。1985年、ソ連にゴルバチョフ書記長が登場して以降、膠着した事態を打開する「機会の窓」は五度開いていた。にもかかわらず、日本政府がそれらを活かせなかったのはなぜか。終戦時外相だった祖父と、駐米大使を務めた父の志を継ぎ、日露領土交渉に心血を注ぎ続けてきた著者が、痛憤と悔恨を込めて綴る緊迫の外交ドキュメント。
目次
ソルジェニーツィンにならって
ロシアとの出会い―青年外交官時代
ゴルバチョフ書記長の登場
ゴルバチョフ大統領の日本訪問
ロシア連邦の成立
ロシア「九二年提案」と東京宣言
ロシア内政の季節
エリツィン第二期政権の始動
クラスノヤルスクと川奈
プーチン首相の登場
イルクーツクへの七ヵ月間交渉
二〇〇一年三月イルクーツク
二〇〇五年三月モスクワ
著者等紹介
東郷和彦[トウゴウカズヒコ]
1945(昭和20)年生れ。東京大学卒業後、外務省入省。祖父は開戦・終戦時の外相。父も外交官。3回の在モスクワ大使館勤務、ソ連課長、欧亜局長など、ロシア関係の業務に都合17年携わる。オランダ大使を最後に2002(平成14)年退官。その後、オランダのライデン大学、米プリンストン大学などで教鞭をとる。2009年ライデン大学で博士号(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
mitei
257
著者が自ら関わった北方領土問題の話をまとめた一冊。宗男事件に巻き込まれて職を追われた後、現在京都産業大学教授、世界問題研究所所長と在野の立場から今もなお北方領土問題に関わろうとする姿勢は共感を覚えた。五度も機会があったのに取り返せないのは日本に問題があったのかもしれないが、ロシア側ももう少し歩み寄るべきだと思った。2016/06/30
Willie the Wildcat
15
ロシア史、日露(旧日ソ)関係、そして日本の対露(旧ソ)対応変遷。元外交官の経験、視点からの描写は時に生々しい。双方の政情も絡み交渉も並大抵の難しさではない。官僚批判を時に耳にするが、国益を念頭に日々業務にあたる方々には敬服の感。一方、最近の政治家で、政党や地元ではなく、国益を念頭にいれた政治力の発揮できる人っているのかなぁ、と今後の外交をイメージ・・・。無理か・・・な。(笑)2011/12/31
ヤギ郎
14
祖父も父も外交官を務めた外交官一家出身の筆者が、外交官人生をかけて取り組んだ日ロ領土問題についてまとめた一冊。本書冒頭では、筆者の退官の原因となった佐藤優背任事件の証言が記される。そして、本書一冊かけて、この事件に行き着くまでの日本とロシア(ソ連)の外交関係が語られる。北方領土問題は、「単なる島」の領土争いではなく、両国の歴史に対する理解や、関係者の政治信条が重くのしかかる。問題に対して、当事者となるために、実際に島へ訪れる。非民主的といわれる外交について、歴史の現場にいた当事者の証言が詰まっている一冊。2021/03/27
sasha
10
著者が外務省を退官する原因になった鈴木宗男事件の記述から始まり、北方領土が何故、ソ連の手に渡ったかから、プーチン政権第一期まで。外交官として交渉に深く関わった著者の回想録というところか。結局はソ連・ロシアにいいようにあしらわれてるってことなのかね。外務省って情報は持っていても有効に使えてないとの印象が拭えない。平和条約締結も、四島返還も、夢のまた夢じゃ駄目なのよ~。2019/06/17
モモのすけ
5
日ソ・露の膠着状態を打開する「機会の窓」は5回あったが日本政府はそれを生かせなかった。「私は双方の交渉当事者に、相手の立場を勘案しながら実現可能な打開策を積み上げていく勇気と決断がもう一つ欠けていたと答えたい」。そして「51対49」の精神が交渉解決には必要とする。2012/09/24