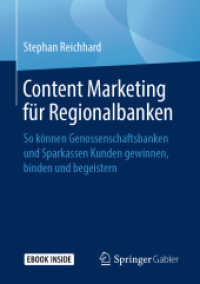内容説明
教職を志す女子大生から、著者に宛てられた一通の手紙。それには、画一的な教育制度の中で痛みを受けた心の叫びが、誠実にしたためられていた。現代日本の学校では、教育に優しさを取り戻すことはもはや不可能なのだろうか?三人の現役教師の豊かな実践記録を通じ、教育の明日を探る第一部。島での心豊かな暮らしを綴った第二部と併せ、生命のいとしさを謳いあげるエッセイ集。
目次
1 優しさとしての教育(きわめて長い手紙;優子の涙;七時間目の子どもたち)
2 島で暮らす(食三題;枇杷の哀しみ;自然の中の住まい;土から学ぶ;鯖のすきやき;若い日の私;大阪放蕩;フィリピンで見たわたしの「祖先」;波照間島の海;ホノルルマラソン奮闘記;河島英五さんとの出会い;叶夢翔氏に問う;ピースボート乗船記;本三題)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
きゅうり
10
教育、食、農業、島での暮らしなどなどのエッセイ集。「いのちの生長に添うことほど楽しくて素晴らしいことはない」あと、何気ない一文の「若者の話はほとんど会話のていをなしていない。…衣服をつけていない声という感じがする」…もう、若者という年でもないけど気をつけます。2016/01/15
Moeko Matsuda
8
エッセイを集めた一冊。かなり古い本だが、ここに書かれている事柄の多くは、30年が経った今でも頷きながら読める内容だ。教育者としてのエッセイ、島暮らしのひとり者としてのエッセイ、どちらも面白い。青臭く尖った印象を受けるのは、社会学を学んだ男性に共通のイメージか。児童文学として知られる(個人的にはむしろ大人向けだと思うけれども…)有名な著作とは違う、作家本人の人となりがうかがえる。その分、この一冊を好むかどうかというのは、まぁ、人それぞれであろうと思われる。2016/03/14
rara
8
灰谷健次郎著「天の瞳」が大好きで、子育ての見本のようにしていた時期がありました。この本は古本屋でたまたま見つけて買いました。もう亡くなられて何年でしょう?いまも残念でなりません。 「生命の自立を助けるためにある教育が、生命を競わせるために利用されているにすぎない。」2013/07/19
てん
7
優しくするって人らしく接することだと思った。 心からの言葉伝えるからこそ時には失敗するかもしれないけど、無難な言葉じゃなくて、ありきたりな綺麗事じゃなくて、もっと相手の気持ちに届くような言葉を伝えたいと思った。 生徒が自由に綴った詩の言葉はまっすぐで、でも奥が深くて考えさせられる。全部を書ききれないからこそその子が背負ってるものを追いたくなる。書き出すことで自分と向き合うから勇気もいるしとても怖い。 教師を演じるのではなくて、1人の人間として生徒に向き合うような人間になりたい。2019/08/12
わわわわ
3
中学〜高校時代に、文庫本がぼろぼろになるまで読み返した本で、当時の自分を救ってくれた言葉がそこらじゅうにある。なかでも、「楽しくなりたい?」「なりたいです」この先生と児童の、「あたりまえのことをきいた」会話が、ずっと支えになった。心も頭もぐちゃぐちゃで、自分が何を望んでいるのか(望んでも許されるのか)さえわからなくなっていた時期、「楽しくなりたい?」と自分に問いかけ、「なりたい」と確認することで、自分を保っていた。十数年ぶりに読んだけれど今読んでも心に響く本だった。2023/08/25