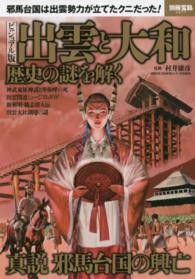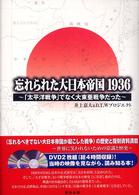内容説明
当代一流の漢学者、依田学海は、譜代佐倉藩の留守居役に抜擢された。江戸留守居役とは、幕府や他藩の動向を調査する情報機関なのだが、実態は、飲食で濫費するだけの堕落した集団だった。剛直の人、学海には屈辱と忍従の日々。やがて、薩長の動きが表面化し、あろうことか、幕府は突然、大政奉還してしまった!藩の運命を担って、学海は一路、京都を目指す。
目次
第1章 剛直の人と留守居役
第2章 江戸留守居の日々
第3章 大政奉還と江戸諸藩邸
第4章 王政復古から戊辰戦争へ
第5章 佐倉藩臨時京都藩邸
第6章 維新政府官吏への道
『学海日録』刊行始末―あとがきにかえて
著者等紹介
白石良夫[シライシヨシオ]
1948(昭和23)年、愛媛県生れ。九州大学大学院修士課程修了。北九州大学講師等を経て、文部省(現文部科学省)入省。現在、教科書調査官。文学博士。中村幸彦・中野三敏の学統を受け、近世文学に軸を置きながら、春日和男・今井源衛・重松泰雄等の薫陶もあり、古代語・古代文学から近代文学・思想史まで幅広い関心を持つ(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
ニッポンの社長ケツそっくりおじさん・寺
43
依田学海(1833〜1909)の幕末翻弄記。新撰組の本が好きな人ならご存知だろうが、負けて江戸に退却した土方歳三の「どうも戦争というものは、もう槍なんかでは駄目です、鉄砲にはかないません」という300年前の信長が聞いたら噴飯物の発言を書き残した人である。佐倉藩の江戸留守居役に任命されるのだが、この留守居役というのは当時の藩の外交官である。インテリの学海はその遊興ばかりの社用族仕事にいらいらしながら勤める。しかし任命されたその年は幕末大詰めの慶應3年!佐幕藩ゆえの右往左往が本書のメインである。2015/09/25
onasu
14
江戸期も最晩年、慶応3年に下総佐倉藩の江戸留守居役に就任した依田学海。その日記を元にした作品。漢籍の知識に富み、新政府にも出仕、後は演劇界にも足跡を残したが、正に歴史に埋もれていた。 政治の舞台が京であったその年、江戸では…。留守居役とは、藩の外交の担い手。だがその実態は、各藩同役との遊蕩と儀礼ばかりと旧態依然。学海は義憤にくれる。 京との距離もある、が結局、何もできないまま、終焉の時を迎える。その後も、佐倉藩存続のため奮闘はするのだが…。 執筆の経緯、そして、新たな方面からの幕末の記述も面白い。2013/09/13
tsubomi
5
2020.04.06-05.16:佐倉藩の江戸留守居役であった依田学海の日記と談話をもとにして幕末の留守居役とはどういう存在だったのか?、そしてその留守居役から見た幕末の日本はどんな風だったのか?ということを解説した本。依田学海は名前を聞いたことがあるものの詳しいことは知らなかった人物。情報を集めたり影で調停をしたり駆け引きしたりと重要な職なのに宴会やくだらない集まりが多くてうんざりしての愚痴や焦燥・苛立ち、官軍・賊軍の認識の変化、任務中に会った要人の数々など興味深い点が多くて幕末好きにはお勧めの一冊。2020/05/16
伊之助
2
面白い。下総佐倉藩江戸留守居役の日記を通して幕末維新の動乱を描いたノンフィクションです。この物語の主人公は、その当時の潮流からいえば、ある意味で普通の藩、普通の武士、しかも負け組みたる徳川家譜代の中小藩の人々。その人々の度重なる大事に翻弄される様、時代の激流に飲み込まれていく様が、すとんと腑に落ちるようによく描かれています。この日記を残したのは、明治に入って漢学、文芸評論、劇作など多方面で名を成した依田学海という方。初めて知る名です。2014/04/15
おっしょう
0
★★★☆☆(3.0)2008/10/31