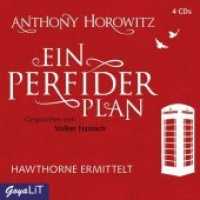出版社内容情報
木田 元[キダ ゲン]
著・文・その他
内容説明
「形而上学」「私は考える、ゆえに私は存在する」「超越論的主観性」―。哲学のこんな用語を見せられると、われわれは初めから、とても理解できそうにもないと諦めてしまう。だが本書は、プラトンに始まる西洋哲学の流れと、それを断ち切ることによって出現してきたニーチェ以降の反哲学の動きを区別し、その本領を平明に解き明かしてみせる。現代の思想状況をも俯瞰した名著。
目次
第1章 哲学は欧米人だけの思考法である
第2章 古代ギリシアで起こったこと
第3章 哲学とキリスト教の深い関係
第4章 近代哲学の展開
第5章 「反哲学」の誕生
第6章 ハイデガーの二十世紀
著者等紹介
木田元[キダゲン]
1928(昭和3)年生れ。山形県出身。哲学者。東北大学文学部哲学科卒。中央大学名誉教授。マルティン・ハイデガー、エドムント・フッサール、モーリス・メルロ=ポンティなどの現代西洋哲学者の主要著作を分かりやすい日本語に翻訳したことで知られる。終戦直後、闇屋で暮らしを立てていたエピソードも有名(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 2件/全2件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ケイ
123
今年の『新潮文庫の100冊』の中の一冊。こういった本を入れるところに、新潮文庫の良心とか意地といったものを感じるのだ。『反哲学…』に惑わされてはいけない。反哲学とは、プラトン以来の超自然的な考え方が哲学とされてきた西洋哲学に対して、そういう哲学を批判して乗り越えようというニーチェの姿勢、考え方である。難しいところもあるが、非常に興味深く、何度も読み返したいと思った。結局は、とてもいい哲学入門書。実存を考えるというのは、プラトン以来の哲学があってのことだと恥ずかしながら初めて知った。2015/09/04
ゴンゾウ@新潮部
114
木田先生は哲学は西欧独自の思想であるから日本人にはなじめないと言っている。まさしく「超自然的な存在」といわれてもぴんとこない。「哲学」の流れを断ち切ることで出てきた「反哲学」も?である。西洋の歴史的な背景がわからないから全体が抽象的すぎてイメージできない。哲学の思想が政治や宗教、自然科学、経済におおきくかかわっていたんだろうけどそういう事象から関連つけてもらえるともっとイメージできたのかなあ。まだまだ基礎知識が足りない。2015/11/19
Hideto-S@仮想書店 月舟書房
105
人類の思想史のガイドブック。一気に読むと頭からプスプスと煙が出そうになるけど、アウトラインを学ぶにはとても良い本。古代ギリシャで、ソクラテス・プラトンにより『自然』の上位概念が生まれ、西洋の価値観の源流となっていった。『超自然』の概念の一つは『神』と呼ばれ宗教が誕生。明治以降日本に入ってきた『哲学』は、自然と共に生きる日本人には真の意味では相容れなかった。19世紀後半、「神は死んだ」と説いたニーチェにより『超自然』を否定する『反哲学』が誕生した。……知の世界を大きな視点で俯瞰し、要点を解説した好著。2015/10/04
うりぼう
100
哲学って、こういうもんだったんだと教えてもらった。冒頭にインタビューに答える形式で作り、素人にも判りやすくとありましたが、私には十分に難しかった。解説のお弟子さんが1回限り名演奏と楽譜の違いと表現されたのが、興味深い。楽譜を読んでいない私は、感心するばかり。「寝ながら学べる構造主義」と同様の感動。「音と言葉」に出てくるニーチェが芸術を高く評価した理由が判った。哲学も単に著書があるのではなく、その時代背景と著者の問題意識から「存在」を解こうと格闘した結果。ニーチェの「肉体の復権」の主張は、その通りだと思う。2010/09/05
SOHSA
73
西洋の思想を、プラトンからニーチェまでの哲学とニーチェ以後の反哲学(反プラトニズム)という括りによって丁寧に解説しており、非常にわかりやすかった。 今まで、代表的な哲学者の思想がどのような位置でどのように関連づけられているのかはっきりしないところがあったが、本書を読んだことですっきりと理解することができた。一般的に難解なことを難解に著すことは簡単だが、平易にわかりやすく著すことは至難のわざである。それをかくも鮮やかにやってのける著者の力量には、ただ敬服するのみだ。まさに入門書に相応しい良書だった。2013/05/26
-
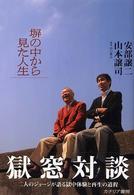
- 和書
- 塀の中から見た人生