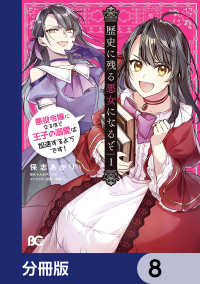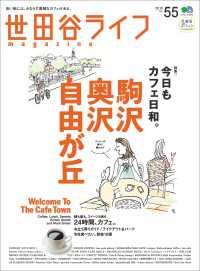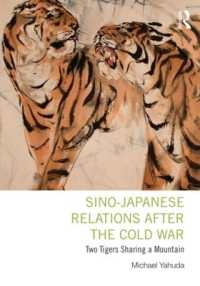内容説明
氷を抱いたベーリング海峡、112歳のインディアンの長老、原野に横たわるカリブーの骨―壮大な自然の移り変わりと、生きることに必死な野生動物たちの姿、そしてそこに暮らす人々との心の交流を綴る感動の書。アラスカの写真に魅了され、言葉も分らぬその地に単身飛び込んだ著者は、やがて写真家となり、美しい文章と写真を遺した。アラスカのすべてを愛した著者の生命の記録。
目次
1 家を建て、薪を集める
2 雪、たんさんの言葉
3 カリブーの夏、海に帰るもの
4 ブルーベリーの枝を折ってはいけない
5 マッキンレーの思い出、生命のめぐりあい
6 満天の星、サケが森をつくる
7 ベーリング海の風
8 ハント・リバーを上って
1 ~ 1件/全1件
- 評価
-





ひのきの本棚
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ヴェネツィア
340
星野道夫の見たアラスカの光景を目の当たりにしたとすれば、世界観があるいは根底から変わるかも知れない、という気がする。人工物が何もない原野を行くカリブーの群れ。マッキンリー山麓の湖畔に佇む1頭のムース。静寂につつまれた森の中で見上げる北極星。それらはまさに「覆いかぶさるような宇宙の沈黙」を私たちに伝えるのだろうか。アラスカは、広大な宇宙の中に浮かぶ地球を、そしてそこに生息する生命といったものを、もっとも身近に感じることができる空間であるのかも知れない。星野道夫の静謐で抒情に満ちた文体が私たちを彼方に誘う。2016/10/31
SJW
173
星野さんが1990年にアラスカに家を建ててから、1993年秋までのアラスカを旅する話が掲載されている。建てられた家を直接見たわけではないが、家についての記述を読むと何か親近感が沸いた。星野さんとではないが、司祭家族と遊びに行った星野家の清里のロッジの雰囲気を感じた。そのロッジで星野さんが小さい頃から自然に親しんで、その雰囲気のロッジをアラスカに建てたのではないかと思う。その後に綴られているアラスカの大自然での旅には憧れを感じるが、自分ではとても生きて戻れそうもない厳しい旅なので、本で読んで思いを(続く)2018/07/29
新地学@児童書病発動中
115
美しい写真と詩的な言葉が一つになって心に沁みる一冊。本書は、著者がアラスカで暮らした時の記録を中心に書かれている。はっと息を飲むような写真が多く収録されていて、この本を読み終わった後も繰り返し眺めた。一番印象に残ったのは、アラスカで様々な人と交流していく点だった。写真家なので一人で行動するのが多いのかと思ったら、星野さんはいろいろな人とのつながりを大切にしている。そこからまた新しい視野が開けることもある。広大な自然の中に身を置いていると、人との絆が貴重なものになるのかもしれない。2018/06/16
はたっぴ
93
何度目かの再読。寒い冬にもっともっと寒い地域の人々に思いを馳せた。ここで出会ったアラスカのパイオニア達はいつも大切なことを思い出させてくれる。生死を分けるような過酷な冬を何度も乗り越えてきた人間は、少しずつ魂のレベルが上がるのかもしれない。星野さんが交流してきたアラスカの友、一人一人の言葉の重みを感じながら身も心も浸りきる。瑣末な出来事に追われていると、つい気持ちがギスギスしてしまうが、そんな時にアラスカのオーロラや未踏の地を想像するだけで霧が晴れたように視界が広がるから不思議だ。清涼剤のような一冊。2018/02/15
naoっぴ
87
すべての生き物は地球上で共存しているという星野さんの言葉のひとつひとつがとても心に響く。どこかでひとごとのように思っていないか、どこかで忘れていないだろうかと、私自身に問いかけながら読んだ。星野さんの住むアラスカの厳しくも清涼な空気を感じながら、自分のいる場所からは想像もつかないほどの大きな自然や、他の命に生かされている事実、文明のこと…やさしい語り口に癒されながらも多くを感じた充実した読書でした。2018/07/30