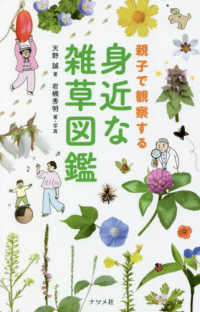内容説明
とりすました石畳の都会から隔たった郊外の街に暮らす私。自らもマイノリティとして日を過ごす傍らで、想いは、時代に忘れられた文学への愛惜の情とゆるやかにむすびつきながら、自由にめぐる。ネイティブのフランス人が冷笑する中国移民の紋切型の言い回しを通じ、愛すべき卓球名人の肖像を描いた表題作をはじめ、15篇を収録した新しいエッセイ/純文学のかたち。三島賞受賞作。
著者等紹介
堀江敏幸[ホリエトシユキ]
1964(昭和39)年、岐阜県生れ。’99(平成11)年『おぱらばん』で三島由紀夫賞、2001年「熊の敷石」で芥川賞、’03年「スタンス・ドット」で川端康成文学賞、’04年、同作収録の『雪沼とその周辺』で谷崎潤一郎賞、木山捷平文学賞、’06年、『河岸忘日抄』で読売文学賞を受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
- 評価
本屋のカガヤの本棚
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ヴェネツィア
203
エッセイといえばエッセイ、小説といえば小説といった境界上の小品群。全部で15の掌編を収録するが、最後の1篇を除いて、他はすべて著者のパリ時代を描いたもの。構造は概ね共通していて、最初はエッセイとして始まり、そこにフランスの小説が介在してくる。やがて、それらが迷宮のごとく渾然と溶け合い、最後はまぎれもなく小説として終わるというもの。いずれも、堀江文学の味わいに満ちた物語群だ。ふと遭遇した少女に始まり、カルスカヤからジンガー(いずれもロシア系の画家)を経て、幻想に融解してゆく「洋梨を盗んだ少女」がことに秀逸。2014/11/27
コットン
107
15のエッセイ・短編集。「おぱらばん」:私が暮らしていた宿舎に中国人が多く住み、その中の先生との関わりや<AUPARAVANT>という言葉からの派生が印象的な作品。最後の「のぼりとのスナフキン」はスナフキン考として面白い。それにしても堀江さんは「洋梨を盗んだ少女」に出てくるイーダ・カルスキー(Ida Karskaya)や「黄色い部屋の謎」のジャン・エリオンと、初めて知る画家をさりげなく作品に忍び込ませるあたり、アートに詳しい手練れな作家ですね~♪2015/11/30
KAZOO
67
堀江さんの小説家エッセイかわからない分野なのですが楽しめる本です。「おぱらばん」という表題の意味は最初のほうですぐわかります。15編の話ですが、「黄色い部屋の謎」は私も昔読んだことがあるフランスの推理小説の話でした。いつもながら堀江さんの文章はすきまなく読まされる感じで非常に印象に残ります。2015/05/30
らむれ
63
いままでなんとも思わずに使っていた「auparavant」っていう言葉が、もう、読んでも発音しても「おぱらばん」としか思えなくなってしまいました(笑)しかも、今までそんなに頻繁には使わなかった単語なのに、発音したいがためにわざわざこの単語をチョイスする始末・・・おぱらばん!ついつい口の中で転がしてしまうこの響き。おぱらばん!おぱらばん!2017/02/23
aika
49
なんだか初めての読み心地です。きらびやかなイメージのフランスにおける、著者が身を持って体感した、いわば陰とも言える現実的な部分と、フランス文学の虚構との融合は、本当に堀江さんにしか書けない文章だなあと思います。異国の地でアウトサイダーが生き延びるための綱渡りの生活に、読んでいるこちらがヒヤヒヤしますが、今まで知ることのなかったフランス文学の香りに包まれて、なんだか、いい意味でへんてこな気持ちになります。丁寧に織り込まれた文章の中に、ちょっとした、あべこべさのようなものがある、これが堀江ワールドですね!2016/10/24