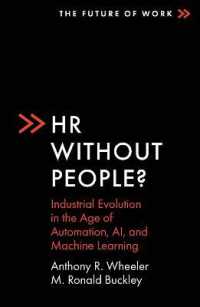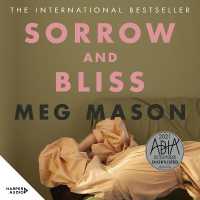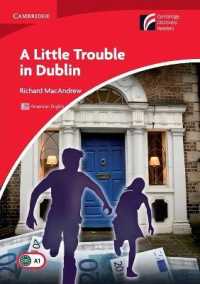内容説明
武藏―。日本が威信をかけて建造した世界最大の戦艦。そこには、仮想敵アメリカ海軍を打倒するという悲願がこめられていた。長崎で極秘裡に進められた建造と艤装。乗員に選ばれた青年たちの喜びと不安。武藏はやがて、戦雲渦巻く外洋へと錨を上げる。十余年の歳月をかけ、生存者への徹底的なインタヴューを敢行。巨艦とそれをめぐる群像を甦らせた、不世出のノンフィクション。
目次
海軍兵学校
三菱長崎造船所
軍艦旗
トラック島
浮かべる城
海軍少尉候補生
甲板士官
パラオ泊地
呉軍港
二隻の駆逐艦
第一次ソロモン海戦
サボ島沖海戦
マリアナ沖海戦
海上輸送
リンガ泊地
出撃
シブヤン海
著者等紹介
手塚正己[テズカマサミ]
1946(昭和21)年、長野県生れ。日本大学芸術学部中退後、劇映画、ドキュメンタリー、テレビ番組の演出に携わる。’89(平成元)年、映像制作会社「シネマジャパン」を設立。’91年、映画「軍艦武藏」の製作・監督を務め、大きな反響を呼ぶ(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
Nobu A
11
手塚正己著書初読。HONZ推薦本。09年刊行。上下巻合わせて1300頁超。読み応え十分とダラダラと長過ぎるは表裏一体。「兵隊は三日に一度しか入浴を許されない。一リットルのぬるま湯を三杯程度」「日本人の目は黒い。アメリカ人の目は青い。この利点を生かして夜戦で勝利を収めたい(西村司令官)」等、所々に興味深い記述があり、当時に思いを馳せる。他方、テーマから外れ脱線することもある。また夥しい数の登場人物。しかも如何せん長過ぎる。関連写真を沢山挿入して欲しかった。集中力が途切れ後半流し読み読了。まだ下巻がある。2024/09/23
鐵太郎
11
武蔵に関しては、吉村昭氏の名著「戦艦武蔵」があります。しかしあの作品で描かれているのは、主として建造の時の、この魔性のフネに人間の域を超えた精力を注ぎ込んだ人々の物語です。武蔵というフネに関わった人々がいかに戦ったか、その後どうなったかまでは書いていません。そして吉村氏の筆は、どちらかというと外から見たジャーナリスト的な視点です。これを戦争のなかにいた人々の視点で、戦記として、後日談として描いたらどうなのだろう。この本はそういう方向で書かれました。2009/10/11
K2
5
綿密に取材して書きこんだのがわかる。戦闘シーンの描写などは、オタクみたいな気分で引き込まれてしまう。戦争には反対だけれど、自分が軍艦やゼロ戦は作る立場になれたらすごくのめりこむとだろう。最近は無人の爆撃機で攻撃する時代になったが、人間が殺されるということを忘れてはいけないと思う。それにしても、アメリカ軍がレーダーで照準した砲弾が日本の軍艦に高い確率で命中し、それに兵士が翻弄されるというような場面は体感巨砲主義にとらわれた上層部におどらされていたずらに若者が生命を落とすことのばかばかしさを感じた。2015/02/16
れごいすと
4
戦艦大和と双璧をなす浮沈艦武藏の、建造からシブヤン海海戦の一次空襲まで。最前線の凄惨さや、当時の世界最高峰のメカニックもさることながら、武藏に乗り込んだ全ての人たちの群像劇がとてもリアルでした。国の為に命を投げ出して無く戦おうとする強い意志は、戦争を知らない自分には理解できず、軍記ものを読むと遠い昔の、自分とはあまり関係の無いような話に感じてしまいがちでしたが、母親から送られたチョコを齧りながら配置につく若い兵隊の心情や、上官や同期との交流などを読んでいると、現代の自分と変わらないのかなと感じました。2011/04/27
長門たつた
4
「武蔵」の建造中から、シブヤン海における第一次空襲前後の辺りまでが書かれている。上巻では主に「武蔵」艦上や、上陸の際のエピソードが中心で、特定の軍人数名を軸に描かれている。こちらでは、時折戦闘の場面があるものの、総じて戦時中ながらもほのぼのとした日常の様子が細かく描かれている。2009/09/03