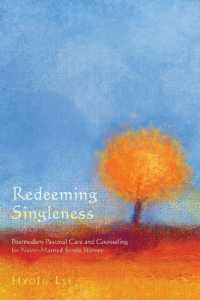内容説明
人間はただ生きることを欲しているのではない。現実の生活とはべつの次元に、意識の生活があるのだ。それに関らずには、いかなる人生論も幸福論もなりたたぬ。―胸に響く、人間の本質を捉えた言葉の数々。自由ということ、個性ということ、幸福ということ…悩ましい複雑な感情を、「劇的な人間存在」というキーワードで、解き明かす。「生」に迷える若き日に必携の不朽の人間論。
著者等紹介
福田恆存[フクダツネアリ]
1912‐1994。東京本郷に生まれる。東京大学英文科を卒業。中学教師、編集者などを経て、日本語教育振興会に勤める傍らロレンスの『アポカリプス』の翻訳や芥川龍之介論などの文芸評論を手がける。戦後は、評論『近代の宿命』『小説の運命』等を刊行。また、国語問題に関して歴史的仮名遺い擁護の立場で論じた『私の國語教室』がある。訳業に『シェイクスピア全集』(読売文学賞受賞)の他、ワイルド、ロレンス、エリオット、ヘミングウェイ作品等がある。劇作家、演出家として劇団「昴」を主宰し、演劇活動も行なう(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 2件/全2件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
鉄之助
304
葬式の儀式性をシェイクスピア戯曲から考察。62年前に発刊、半世紀以上も前の古い本だが、去年、第11刷と、大変息の長い版を重ねてきているロングセラー。「葬儀は、死から生への橋渡しをする。そこに、私たちは劇場における営みと全く同じものを見る。遺族は悲劇の主人公であり、会葬者は観客である」と、葬儀の重要性を喝破。しらじらしい虚礼と感じられようとも、故人を失った悲哀感、日常生活から断絶させるために「型」が必要で、このいかにも悲しんでいるという「型」によって遺族は癒される。2024/09/13
ナマアタタカイカタタタキキ
81
薄い割になかなか読み応えのある一冊だった。反面少々くどいかもしれない。昨今“演じる”という言葉を表面的に用いる時、それは他人の目を意識しながら誇張表現に走る姿を想起させるだろう。それとは別の、著者が挙げた“演戯”について説明するならば──未来を想定せず、過去に遡ることもせず、ただ直向きに現在へ徹する、自分という人間が今に在るという感覚へ没頭する。そのような営みによって、部分的な生の感覚から離れ、全体へ回帰しようすることで、人生の必然性へ触れんとする試み、とでもいうべきだろうか。ここでの必然とは、→2021/11/13
てち
76
自分とは何か、個性とは何か、自由とか何かと問われることが多い昨今に対して一種の答えを導き出している本作。個性とは自分が演じたい役割であるし、人間は自由でなく必然を求めその中で生きたいと思うものであると筆者は考えている。つまり、舞台のように決められた役割をその瞬間に演じるといったことである。なるほど、一理あるかもしれない。2023/01/05
がらくたどん
60
憑依系俳優のアイデンティティーを巡る面白いエンタメ作品を読みながら。多才な著者だが、私の中ではシェイクスピア翻訳者であり劇作家。演技者は「劇」というその時々の世界の中でそれぞれの役割という個性を纏う。表題の「劇的」は激しさ・起伏の大きさが前面に出た通釈より文字通り人生という「劇」を生きる者というニュアンスと理解している。「個性などというものを信じてはいけない」「それは自分が演じたい役割ということにすぎない」という分析は「本当の自分」「個性」というものへの甘美な誤解を揺るがすが人生の自由度を上げる気がする。2024/09/13
ω
58
なかなか面白く読んだ。「私たちが欲するのは自由ではなく、事が起るべくして起る必然性(=宿命)だ」「自由の原理は私たちに快楽をもたらすかもしれぬが、けっして幸福をもたらさぬ」人間とは演戯(現実の拒否と自我の確立のための運動)をするという意味で、「劇的」なるものである。 ウン、とりあえずハムレット読んでから出直そう😂2022/06/19