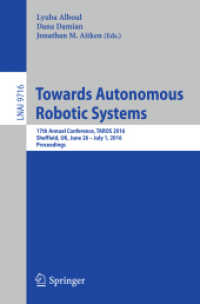出版社内容情報
震災発生翌日から被災地入りした笠井。目の前のご遺体、怯える被災者たち。そのとき報道人は何ができるのか――渾身の被災地ルポ。
2011年3月11日午後2時46分、東日本大震災発生。翌日から笠井の現地取材ははじまった。目の前で発見されるご遺体と泣き崩れるご家族。どう言葉をかけたらよいのかわからなかった。「水がない」と訴える方の声を聞きながら、取材車に積んである水を目の前の方たちに配るべきか悩んだ。報道人としての葛藤や失敗、今も続く被災者との交流を綴った、渾身の震災ノンフィクション。
内容説明
2011年3月11日午後2時46分、東日本大震災発生。翌日から笠井の現地取材ははじまった。目の前で発見される遺体と泣き崩れる家族。どう言葉をかけたらよいのかわからなかった。「水がない」と訴える人の声を聞きながら、取材車に積んである水を配るべきか悩んだ。何のためにここに来たのか―報道人としての葛藤や失敗、今も続く被災者との交流を綴る渾身の震災ノンフィクション。
目次
第1章 僕は何のためにここへ来たのか 震災発生!報道人は“食べて”はいけない
第2章 72時間超!報道人は“乗せて”はいけない
第3章 1週間!報道人は“泣いて”はいけない
第4章 東北人と関西人
第5章 被災地で出会った忘れられない人たち
第6章 2カ月…3カ月…そして半年
第7章 あの日から5年―
著者等紹介
笠井信輔[カサイシンスケ]
1963(昭和38)年、東京生れ。’87年、早稲田大学卒業後、フジテレビ入社。アナウンス室所属。現在は「とくダネ!」に出演(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
佐島楓@入院中
Nazolove
ツキノ
お昼寝ニャンコ
ゆかり