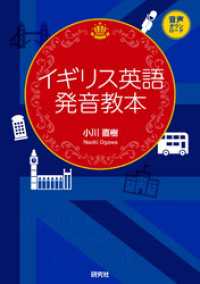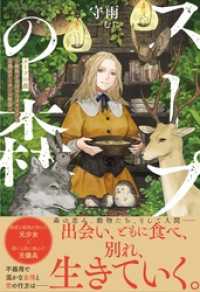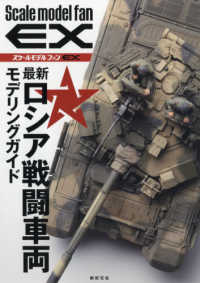出版社内容情報
三絃、画工、糸染、活花……。男との宿縁や恋情に後ろ髪を引かれつつも、芸を恃みにして逆境を生きる江戸の女たちを描いた短編集。
早くに両親を失い、同じような出生の二人は、幼い頃から互いを支え合ってきた。紗代乃は活花、藤枝は踊りが生き甲斐だった。だが、いつしか二人は、一人の男に翻弄されていた(表題作)。子を置いて離縁し、糸染に身を捧げる萌に所帯を持とうと言い寄る男が現れる(「秋草風」)。三絃、画工、根付、髪結……。人並みの幸福には縁遠くても、芸を恃みに生きる江戸の女を描く全七編の短編集。
内容説明
早くに両親を失い、同じような出生の二人は、幼い頃から互いを支え合ってきた。紗代乃は活花、藤枝は踊りを生き甲斐にして。だが、いつしか二人は、一人の男に翻弄されていた(表題作)。子を置いて離縁し、糸染に身を捧げる萌に所帯を持とうと言い寄る男が現れる(「秋草風」)。三絃、画工、根付、髪結…。人並みの幸福には縁遠くても、芸をたのみに生きる江戸の女たちを描く芸道短編集。
著者等紹介
乙川優三郎[オトカワユウザブロウ]
1953(昭和28)年、東京生れ。千葉県立国府台高校卒。’96(平成8)年に『薮燕』でオール讀物新人賞、’97年に『霧の橋』で時代小説大賞、2001年に『五年の梅』で山本周五郎賞、’02年に『生きる』で直木賞、’04年に『武家用心集』で中山義秀文学賞をそれぞれ受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ふじさん
56
16冊目の乙川雄三郎の時代小説。再読の最後の一冊。三弦・蒔絵・茶道・画工・根付・糸染め等。これらの芸道に、男と女、あるいは親と子という人間関係のしがらみが複雑にからまる。それぞれがある時は睦み合い、ある時は反発しながら現実を乗り越え、芸の本質に少しずつ近づく人生の闘い描かれる。人並みの幸せには縁遠くても、芸を頼みに生きる健気な女がいる。まれにみる芸道短編集だ。 2020/08/12
みっちゃんondrums
23
女ひとりが生きていくために、芸事を身につけた女たちの物語。みな覚悟がある。背筋がすっと伸びた姿が思い浮かべられる。江戸時代ものを読み慣れていないせいか、日本の芸事に詳しくないせいか、わからない専門用語が多かったが、美しい日本語で、しっとりとした文章だった。2019/02/05
キムチ
16
今更ながら、芸事の大半はお抱えと云う状況で発展を遂げてきた事を痛みを伴って感じる。一般、日陰と「同じ女」でありながら色分けするのは不本意だが。文学の題材にはうってつけと云うのも逆説めいて。 乙川氏の文体は実に流麗、いつも裏切らない。「竹夫人」を読みつつ、坪内逍遥夫人を書いたものを思い出し、イメージが具現する。 古今の東西問わず、男が少女ともいえる娘をおんなに育てて行く事実は知れているところ。 で、その娘の心は。「秋野」の千津のつぶやきなのだろう。 その傍らに「在った」事物の描写が余韻をかもす。2013/06/20
michel
13
★3.2。時代短編小説。三味線、茶道、華道、舞踊…芸道に生きる女たちが、男、家族、友との交わりの中で清廉な生き方を見せてくれる。美しい生き方。2021/03/08
niaruni
11
ひとつの芸事を極めようとすることと女であることは両立しない? とんでもない。何事かを極めようという一途さ、そのために努力を惜しまない律儀さ、それを実践するために日々に工夫を凝らす生真面目な生き方、不要なものをすっぱりとあきらめる潔さ、どれも女の得意とするところ。そういう部分で至芸は女の本質だ、と本書で改めて気づかされた。女のいいところを描かせるとこの作者は本当に巧い。そして、一本筋の通った女のまわりの、ちょっと駄目な男に向ける眼も厳しすぎない。それと端正な日本語。だから読んでいて気持ちいいのだと思う。2012/07/19