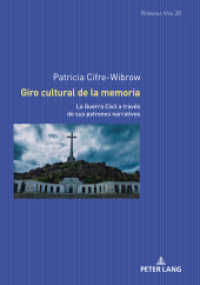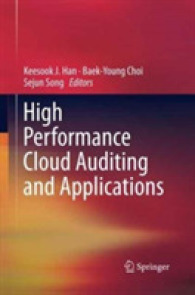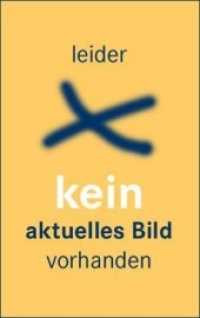内容説明
まぎれもない「兵士」の集団でありながら軍隊とは呼ばれない、いまだに国民の拒否反応も根強い―。そんな「日蔭者」の存在、自衛隊の隊員たちは、何を思って日夜、厳しい訓練に耐えているのか。護衛艦やレンジャー訓練への同行など徹底した密着取材により、彼らの素顔を浮き彫りにする。日本人が直視してこなかった「戦後」を敢えて問うた渾身のノンフィクション。新潮学芸賞受賞。
目次
第1部 鏡の軍隊
第2部 さもなくば名誉を
第3部 護衛艦「はたかぜ」
第4部 防人の島
第5部 帰還
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ヴェネツィア
321
本書は新潮学芸賞を受賞しているが、それも当然の優れたルポルタージュである。ここでいう「兵士」は兵卒の意味ではなく、現役自衛官(ただし幕僚は含まなず、あくまでも現場の将校、下士官、兵士)のことである。取材は陸上、海上、航空(今回は奥尻のレーダー基地)、さらにはカンボジア派遣のPKO部隊におよぶ。それぞれの部署に携わる自衛官の声が収録されているのだが、そこには世間との、また自衛隊を統括するはずの政府との間とも大きな解離(もしくは断層というべきか)がある。とりわけ、それが顕著に現れたのがカンボジアPKO⇒2023/09/01
saga
61
陸自のレンジャー訓練に臨む幹部隊員の裏事情。海自では、建造される護衛艦の総定員に見合わない乗組員数に苦しむ曹士クラスと、官僚主義的な幕僚の姿。空自は、離島の基地が取材対象。93年に発生した北海道南西沖地震による救援活動の描写は生々しかった。島民と、自衛隊員とその家族との確執も描かれ、閉鎖的な地域に根差す困難さを感じた。第五部はPKO派遣問題だ。政情不安なカンボジアで、銃に装弾しないでの歩哨、命令がなければ発砲できない、万が一発砲したら自己責任なんて、今さらながら自衛隊が置かれた立場と法の矛盾を感じる。2021/11/16
hatayan
26
1995年刊。現場で働く自衛隊員に密着したノンフィクション。 レンジャー訓練、奥尻島を襲った津波、カンボジアのPKO派遣などで隊員が何を考え、悩んで行動したかが600頁に濃縮されています。 刺さったのは、PKOから凱旋帰国する隊員を日本に残された隊員が笑顔で出迎えたときに裏で渦巻いていた心情。「出迎えになんか行きたくなかった。選ばれなかった人間にとっては、おまえたちの勇姿なんか見たくもなかった。笑い顔作って出迎えていたけど、本当は辛かったんだ」。 自衛隊員の生身の声にこれほどまで肉迫した作品を知りません。2019/03/22
りょう君
20
素晴らしい内容であった。ノンフィクション作家の力作で新潮学芸賞を授賞した作品。作者は自決した三島由紀夫に強い思い入れがあり、自衛隊の市ヶ谷で起こした事に「物書き」として、気持ちの整理を付けようとしたかの様であった。奥尻島の震災の悲惨な様子や、PKO活動の極限の緊張感など隊員に対するルポは価値があると思う。93年の軍事政権下のカンボジアにおける自衛隊のPKO活動は、今の学生世代は教科書の知識かも知れない。当時としては国内で訓練のための訓練の自衛隊が初めて海外で活躍した出来事だったのだ・・2016/04/06
たか。
8
ほとんど報道されない自衛隊員の考えや想いそして自衛隊員であるが故の苦悩が少しだけわかった気がする。意外だったのがPKO派遣関連。派遣された人・されなかった人・派遣から戻ってきたその後、等々。ちょっと古いけど読む価値はあります。2014/01/18