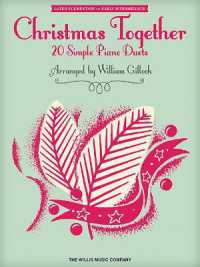内容説明
東西両軍の兵力じつに十数万、日本国内における古今最大の戦闘となったこの天下分け目の決戦の起因から終結までを克明に描きながら、己れとその一族の生き方を求めて苦闘した著名な戦国諸雄の人間像を浮彫りにする壮大な歴史絵巻。秀吉の死によって傾きはじめた豊臣政権を簒奪するために家康はいかなる謀略をめぐらし、豊家安泰を守ろうとする石田三成はいかに戦ったのか。
著者等紹介
司馬遼太郎[シバリョウタロウ]
1923‐1996。大阪市生れ。大阪外語学校蒙古語科卒。産経新聞文化部に勤めていた’60(昭和35)年、『梟の城』で直木賞受賞。以後、歴史小説を一新する話題作を続々と発表。’66年に『竜馬がゆく』『国盗り物語』で菊池寛賞を受賞したのを始め、数々の賞を受賞。’93年には文化勲章を受章。“司馬史観”とよばれる自在で明晰な歴史の見方が絶大な信頼をあつめるなか、’71年開始の『街道をゆく』などの連載半ばにして急逝。享年72
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ヴェネツィア
558
上巻の主人公は石田三成。そして、陰の主役はもちろん徳川家康だ。もっとも、この巻の終わり辺りからは、ずいずいと前面にまかり出てくるのだが。秀吉没後の権謀術策渦巻く武将たちの世の中で家康腹心の家臣の一人、本多正信などは「世の中は実に面白い」と言うのだが、私などはむしろいっそ投げ出したくなってしまう。数ある登場人物たちの中で自分がなりたい(もしくは、ならなければならない)一人を選ぶとすれば、私なら織田有楽斎がいい。家康の器量もないし、はたまた三成ほどの忠誠心や志もない。かといって加藤清正のようなのも嫌だし…。2017/04/08
ehirano1
230
三成が誰かに重なる・・・・・そう、それはミスター原理原則且つ、ミスター唐変木の竜崎(隠蔽捜査シリーズ/今野敏)!しかし、相手はもはや「全てを知る者」と言っても過言ではない家康で、その知略の前では理性なんぞは風前の灯。加えて、家康の側近もこれでもかと言わんばかりにエグイ。今後の対立は既に結果が分かっているとは言え、彼らの対決にワクワクが止まりません。2025/09/13
mura_ユル活動
191
久しぶりの司馬氏、44冊目。関ヶ原はどう描いているのだろうと。秀吉の病状、三成の人、家康、とその周りの環境・状況で始まる序章。秀吉の遺言を守らない家康。人徳・功名・過去の恩、将来性、評判、人望、色々なものが交わる。藤堂高虎って主家をこんなにも変えたんだとわかる。「人は利害で動く、正義では動かない」。石田三成が奉行を退官して佐和山城へ。故秀吉の遺言の家康は伏見城へを策略により、秀頼のいる大阪城へ。加賀討伐諸事があって上巻終了。「余談だが」は数えただけでも6箇所あった。次巻へ続く。2019/07/28
yoshida
175
8月の映画公開に向けて再読。上巻では前田家が家康に屈するまでを描く。豊臣秀吉の側近であり五奉行筆頭の石田三成を主人公に、秀吉の死後に天下を乗っ取ろうとする徳川家康との戦いを描く。惜しむらくは三成の横柄さ。また、豊家は秀吉一代で政権を築いたため有力な一門衆がおらず、譜代も尾張閥と近江閥に分裂し、家康に付け入る隙を与えてしまった。三成の潔癖さと気概。島左近の格好良さ。家康と本多正信の希代の謀略。豊臣の明るさと、徳川の暗さ。三成の義と、家康の利。鮮やかなコントラストを描きながら、関ヶ原の大乱に向け時代は動く。2017/07/17
yoshida
161
初めて読んだ司馬遼太郎。 石田三成は豊臣政権を守る為、軍師の島左近と共に、格の違う徳川へ挑む。義と利。理想と実利。