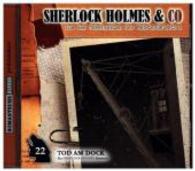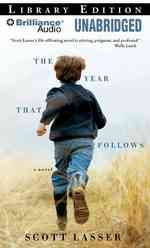内容説明
「私が今、一番希求するのは、静かに人生を退場する方法である。それは死ぬことだけではない。どこかこの地球の片隅で、孤独にも耐え、静かに自分自身と向き合って観想の日々を送ることだ」―マダガスカル、インド、カメルーン、ブラジル…世界各地で極限的貧困の現場を踏破した作家が、自らの老いと向き合いつつ、生と死の現実を冷静な観察眼で切り取ったレポート・エッセイ。
目次
指さす少年
復讐代理人
或る修道女の帰天
或る変容
一番怖い批評家たち
愚かな旅支度
定年以後
李登輝氏の靖国参拝
僻地とはいかなる場所か1
開校式の日―僻地とはいかなる場所か2〔ほか〕
著者等紹介
曽野綾子[ソノアヤコ]
東京生れ。1954(昭和29)年聖心女子大学英文科卒業。同年発表の「遠来の客たち」が芥川賞候補となる。’79年ローマ法王よりヴァチカン有功十字勲章を受ける。’93(平成5)年日本藝術院賞・恩賜賞受賞。2003年に文化功労者。1995年12月から2005年6月まで日本財団会長(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
シュラフ
28
そこに書いてあるのは極限的貧困生活。マダカスガルへの農業支援で作物がよく採れたという現地の農民に"いま一番したいことは"と問えば、"家族でお腹いっぱい食べたいです"との答え。インフラも医療設備も整っていないから、難産の産婦も何時間もかかって戸板で運ばれてくることもあるという。ひるがえって日本はどうだろう。下流だの、貧困だの、生活が苦しいだの、とか言うが、甘えすぎではないだろうか。お金を得たければ働けばいいだけの話。全国津々浦々にインフラが整った生活環境の中で日本人の生きる力は減退しているのではなかろうか。2016/09/18
雲をみるひと
19
曽野綾子氏の自身の活動が主で反省の振り返りも含まれたエッセイ。少しそれが出過ぎているきらいもあるが、作者が信念を持って活動されていたことがよくわかる。マダガスカルなどの途上国で活動されている日本人の話がよく出てくるのは作者ならでは。宗教と切り離されてはいないが、それほど宗教的でないので万人にとって違和感なく読める本だと思う。2024/06/02
あや
10
聖書の言葉に「右の手をしていることを左の手に伝えるな」的な言葉があるという。それは良い行いをしてもひけらかすべきではないという意味だという。著者はアフリカのカジノで当たったお金をきっかけに恵まれない貧困国に派遣された修道士を援助する団体を40年務めてきた。寄付金が純粋に寄贈先に利用されているか私費を投じて確認されてこられた。曽野綾子さんのエッセイの読者ならよくご存知の逸話だが曽野綾子さんご自身はエッセイの中でしかあまり語られないのは、「右の手をしていることを左の手に伝えるな」的な聖句を守られていらっしゃる2021/10/09
みずいろ
5
「生きようとしても生きられない場合もある。死にたいと思っている人でも死ねない時がある。私にも人並みな生に向かう本能はあるが、同時にかなり強い諦めが用意されていた。そうでなければ、不運な運命の下に死んだ人たちに対して申し訳ないと思うのである。」悟りにも似た諦念が底にあるからこそ、著者は周りのすべてのことをまっすぐ見定められるのかなと思った。情報が溢れるこの社会で、どんなことに目を止め、考えなければならないのかということを教えられた。三階建ての校舎が、子供にとって人間復活の場になりうるという話が印象的だった。2014/03/15
ふたば子
4
きっぱりとしたきつい、或る意味とりつく島な物言いが賛否をわける作家である。世間におもねることのない語り口は私にはいちいち尤もに感じられる。彼女のもつ「寄付・援助」に対する認識は、まさに日本人が決定的に欠いてるものではないかと常々個人的にも感じている。2011/12/28
-

- 和書
- 大塚康生 道楽もの交遊記